「うちの子、小学生なのに毎日ゲームばかり…」と悩んでいませんか?
実は、向き合い方を工夫すれば、依存を防ぎながら勉強や遊びも両立できます。
 ナト
ナト私の子供達も、マイクラやロブロックスに夢中で、毎日ゲームばかりしていた時期がありました。
そのとき実践して効果のあった改善策を、具体的に紹介します。
本記事では、家庭でのルール作り、長期休暇のスケジュール管理、時間制限アプリの活用、さらにゲームを教育に活かす方法まで解説します。
読めば「どう注意してもやめない」「生活リズムが乱れる」といった不安が解消され、親子で笑顔の時間が増えるはずです。
今日から始められる実践的なヒントを、わかりやすくお届けします。
ぜひ、参考にしてみてください!
- ゲームばかりするようになる理由
- ゲーム時間を減らす具体的な方法
- ゲームのしすぎを改善させるコツ
- ゲームを教育や成長につなげる活用法
小学生がゲームばかりするようになってしまう理由


小学生がゲームばかりになってしまう理由、実はちゃんとあるんです。
- 自由時間の増加
- 友達とのコミュニケーション手段に変化
- 親の目が届かない時間帯がある
- 厳しい制限が逆効果になることも
まず、大きいのが自由時間の増加。
特に夏休みや冬休みは学校がなくて時間を持て余してしまいがちですよね。
それに今は、昔みたいに子供だけで外遊びをさせるのも難しい時代。



私たちが小学生の頃は友達の家に電話して遊びに行けましたが、今は心配で絶対無理ですよね。
最近のゲームは友達とのオンライン交流が当たり前になっています。
もはや単なる娯楽ではなく、友達とのコミュニケーションの場なんです。
共働き世帯が増え、保護者が忙しくて目を配れない時間は、手軽なゲームに頼りがち。
「ゲーム禁止!」と一方的に制限すると、かえって反発して隠れてやることも。
こうした環境の変化が重なって、気づいたらゲーム中心の生活になってしまうんです。
夏休み・冬休みは特に要注意!


長期休暇は、小学生がゲームばかりするようになりやすい危険な時期です。
生活リズムが崩れて自由時間が一気に増えるのが主な原因ですね。
夏休み・冬休みは宿題を後回しにして、ゲームが最優先になりがち。
私も子供の夏休み中「今日は何してたの?」と聞くと「ゲーム」だけ。
この返答には本当に焦りました。



昔みたいに「○○君遊ぼ~」と友達の家に行くのも難しい時代ですよね。
特に共働き世帯が増えた今、家でお留守番させるケースも多くなっています。
家にいても特にやることがなく、結果的にゲーム時間が極端に増えてしまうんです。
子供のゲーム依存は親のせい?


「ゲーム依存は親のせい」と聞くと、ドキッとしますよね。
でも、これは半分正解で半分不正解だと私は思います。
子供の性格による部分もあるからです。
実際、手放しでゲームをさせていても自分でやめられる子もいます。
でも大人がサポートしないと、ゲームばかりになってしまう子も確実にいる。
だから「全部親のせい!」と決めつけるのは違うと思うんです。
ただし、ゲームばかりなのを知っていて改善しようとしないのは「親の責任」です。
確かにルールを作らずに放任すると、依存傾向が強まるケースがあります。
でも過剰に制限しすぎると、今度は反発して隠れて遊ぶようになることも。
大切なのは、親が一方的に禁止するのではないこと。
子供自身が納得して守れるルールを一緒に作るのがポイントです。
責めるより、一緒に改善策を考える姿勢が親子の信頼関係を育みますよ。
ゲームばかりする子供の末路とは?


小学生のうちからゲームばかりの生活を続けると、以下のようなリスクが考えられます。
- 学力低下(宿題や勉強時間の減少)
- 体力低下(運動不足による持久力や筋力の低下)
- 睡眠不足(夜更かしや朝寝坊の習慣化)
- 対人関係の減少(友達との直接的な交流が減る)
もちろん、すべての子がこうなるわけではありません。
でも長時間のゲームは生活バランスを崩しやすいのも事実なんです。
実際に「子供のインターネットゲーム障害の背景因子と外来治療経過」では、依存的なゲーム・スマホ利用による昼夜逆転や学業・健康問題、不登校傾向などが具体的に報告されています。
また、長崎県の小・中・高校生約4000人を対象に、新型コロナ休校後のゲーム依存症実地調査では、「ゲーム依存症の可能性がある」とされた児童生徒は7%という結果が出ています。
「うちの子は大丈夫」と思っていても、気づいたときには手遅れということも。
早めの対策が何より大切ですね。
これらのデータから見えてくるのは、ゲームばかりの状態は生活リズム・勉強・健康に影響を及ぼす可能性が高いということ。



「だからゲームが悪い」ということでは決してありません。
実は、ゲームが教育に良い効果をもたらすという研究や論文も数多くあるんです。
教育的観点でゲームに関心を持つ人々を対象に行われた調査では、多くの方が「ゲームから役に立つ学びを得た」と回答しています。
また、東京大学とベネッセ教育総合研究所の共同研究、「子供のICT利用に関する調査」も行われました。
ここでは、保護者のサポート次第で、ゲームと上手に付き合いながら良い効果を得られるという調査結果がでした。
つまり、ゲームとの付き合い方を工夫すれば、教育に良い効果をもたらしてくれます。
小学生のゲームばかりする生活を改善させるコツ


小学生のゲーム漬け生活を改善するには、禁止よりも信頼関係づくりと生活習慣の見直しが大切です。
つい「ゲーム完全禁止」にしたくなるけれど、「ゲーム好き」を活かすほうがずっと効果的。
改善のための5つのコツは以下の通りです。
- 親子で話し合いながらルールを決める
- 夏休み・冬休みは効果的なスケジュール管理
- 時間制限アプリ・ペアレンタルコントロール活用
- 外遊びや運動を自然に取り入れる
- 勉強とゲームを両立させるご褒美ルール
こうした取り組みを続けることで、子供はゲームと勉強・遊びを両立し、自分で時間をコントロールできる力を身につけられます。
親子で話し合いながらルールを決める
一方的にルールを押し付けると守られにくいです。
私の家では「ゲームは1日〇時間」「宿題が終わってから」というシンプルなルールを子供と一緒に決めました。



ゲームによって使い分けることも、最初に決めておくと良いですね!
自分で決めたルールは守りやすく、トラブルも減ります。
夏休み・冬休みは効果的なスケジュール管理
長期休暇は自由時間が多い分、計画的に過ごさないとゲーム漬けになりがち。
そこでおすすめなのが時間ごとにやることを決めた表作りです。
午前は勉強や家事のお手伝い、午後は自由時間といった感じですね。



2パターン以上準備しておくと、子どもも飽きずに続けてくれますよ!
また、1日で必ずやるべきことを決めてあげると習慣化もしやすいです。
例えば我が家では「読書」「タイピング練習」「掃除(必ず1か所)」の3つ。



最初からたくさん入れても続かないので、1~2個がちょうど良いですよ!
こうした工夫を組み込みながら親子で1日のスケジュールを決めていくと、ゲーム時間も自然とコントロールできるようになります。
時間制限アプリ・ペアレンタルコントロール活用
Switchやスマホには、使用時間を制限できる機能があります。
特にSwitchの「みまもりSwitch」やiPhone/Androidのスクリーンタイム機能は便利。
それぞれの機能でできることは、以下の通りです。
- アプリやWebサイトごとの利用時間を詳細に確認できる
- アプリの使用時間に制限をかけ、制限時間を超えたら使用できなくする
- 支払い・課金の制限設定
- ゲームのプレイ時間管理・制限
- 遊んだゲームやプレイ時間の確認
- 暗証番号による設定保護
親が口で注意するよりも、機械的に制限する方が揉め事を減らせます。



やるゲームが決まっている場合は、ゲーム側で設定するのも効果的ですよ!
外遊びや運動を自然に取り入れる
「外で遊びなさい!」と言っても、動かないことがほとんどですよね。
そんなときは親も一緒に遊んで、その中に運動を組み込むのが効果的です。
親と一緒に体を動かすのが、楽しい思い出作りの最大のコツなんです!
楽しい記憶とセットにすることで「また行きたい!」と思ってもらえます。
今までゲームに頼ってしまっていた分、家族でお出かけするときは外遊びや運動を一緒に楽しんでみてください。
勉強とゲームを両立させるご褒美ルール
「宿題が終わったら1時間ゲームOK」など、ゲームを報酬として使う方法は効果的です。
ただし、ご褒美時間が増えすぎると本末転倒になってしまいます。
上限時間を必ず決めておくのがポイントですね。
苦手な科目がある場合は、ゲーム感覚で学べるアプリも活用してみましょう。
ゲームと勉強を同時にできるので一石二鳥です。



参考記事もチェックしてみてくださいね
算数が苦手なお子さんには、こちらで楽しく学べるアプリをご紹介しています。
また、web上でできる学習ゲームについても詳しくまとめました。
どちらも無料で試せるものばかりなので、ぜひ活用してみてください。
ゲームばかりする子供にイライラ…親が感情的にならない工夫


正直、親も人間ですから子供がゲームばかりだとイライラするのは当然です。
感情的になる前に深呼吸→別室で一息→冷静に話すを心がけましょう。
さらに「何時までゲームする予定?」と質問形式で伝えると効果的。
子供自身が行動をコントロールしやすくなるんです。
ゲーム好きを教育的に活用する方法
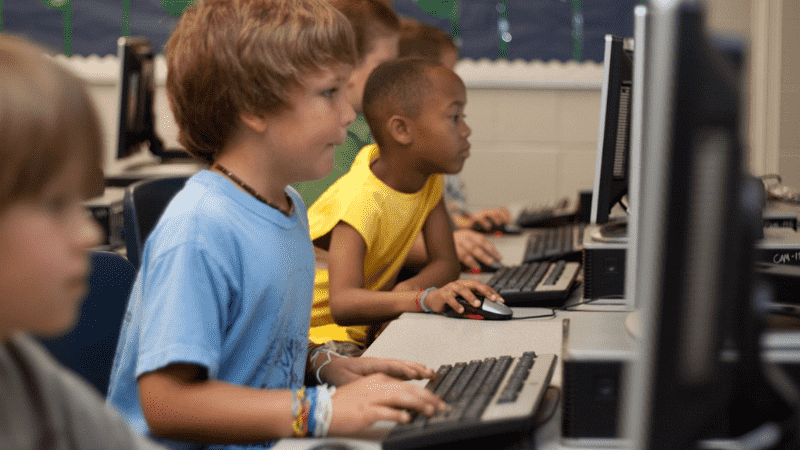
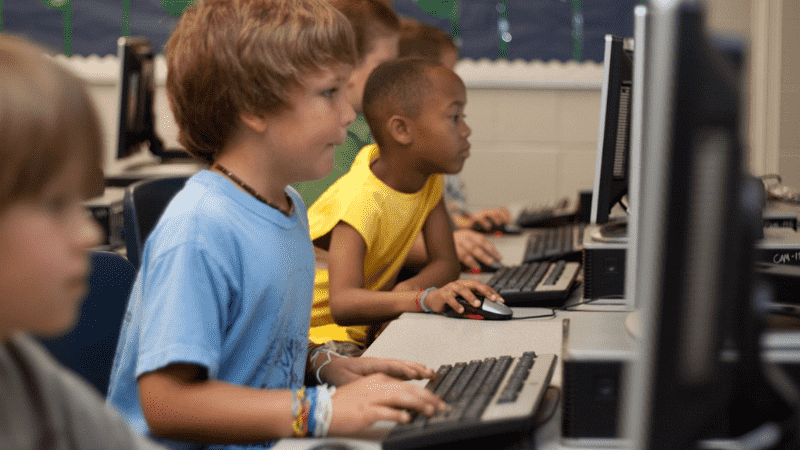
「ゲーム=悪いもの」と思われがちですが、使い方次第で立派な学びのツールになります。
プログラミング的思考や英語力、協調性など、遊びながら身につく力は意外と豊富です。
ゲーム好きなお子さんには、以下のように教育的な活用が可能です。
- ゲームが教材の習い事をさせる
- 親子で一緒に学びながら遊ぶ
- 知育・教育に良いゲーム作品を選ぶ
ゲームが教材の習い事をさせる
MinecraftやRobloxは、実は遊び感覚でプログラミングが学べる優れものなんです。
自分で建物や仕組みを作る過程で、論理的思考や問題解決力が自然と身に付きます。
さらに英語音声や字幕を使えば、遊びながら英語にも触れられます。
オンライン講座や教室を活用すれば、学びと遊びを見事に両立できますよ!
中でも、オンラインで学べる「デジタネ」は、子供が飽きずに続けやすい工夫が豊富です。
デジタネの詳しい内容は、以下の記事で解説しています。
また、以下の記事では学習効果の高いゲームをまとめて紹介しています。
ぜひ、参考にしてみてください。
親子で一緒に学びながら遊ぶ
同じゲームを一緒にプレイすると、ルールやマナーを実践的に教えられます。
協力プレイ型のゲームなら役割分担や意思疎通が必要になり、親子の会話も自然と増えるんです。
「この場面ならどう動く?」と話し合うことで、判断力やチームワークも磨かれます。
遊びの時間が、気づけば教育の時間にもなっているという一石二鳥の効果!
「ポケモンユナイト」はチーム戦なので協力プレイにピッタリです。
実はこのゲーム、ベネッセの学習プログラムにも採用されています。



ゲームを通じて学べることがたくさんあるという証拠ですね。
こちらの記事で、ポケモンユナイトの魅力について詳しく解説しています。
ぜひ参考にしてみてください。
知育・教育に良いゲーム作品を選ぶ
パズルやクイズ形式のゲームは、集中力や発想力を自然と高めてくれます。
地理や歴史をテーマにした作品なら、遊びながら楽しく知識も増やせて一石二鳥。
年齢や興味に合ったタイトルを選ぶことで、子供も飽きずに続けられます。
選ぶときは口コミや専門サイトを参考に、安全で教育効果の高いゲームを見つけましょう。
知育・教育に効果的なゲームをもっと知りたい方へ
子供の知的教育に役立つSwitchソフトについて、こちらで詳しくご紹介しています。
また、Minecraftが子どもの教育に与える効果についても、実体験を交えて解説しました。
どちらも実際に試して効果を感じたものばかりなので、ぜひ参考にしてくださいね。
まとめ|ゲームとの上手な付き合い方で親子関係も良くなる
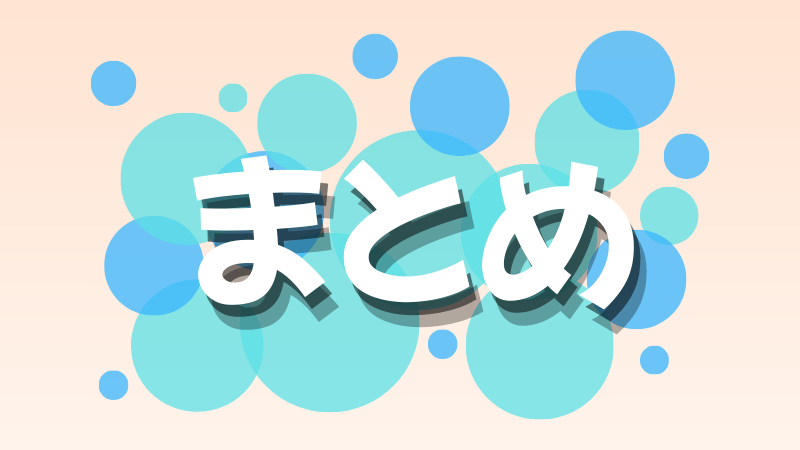
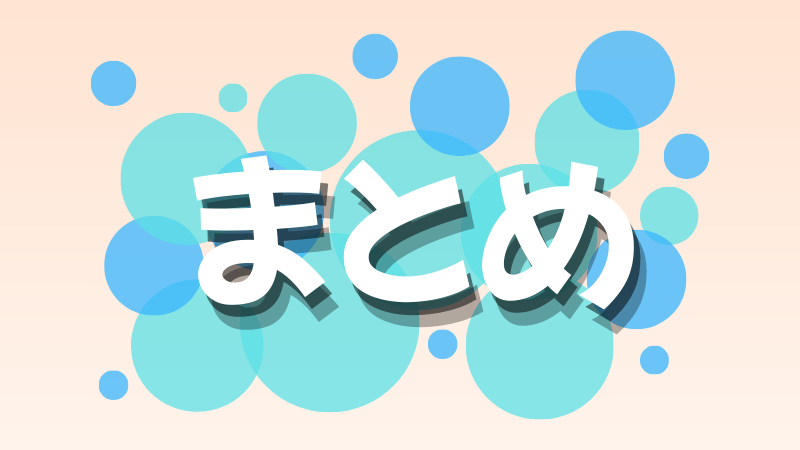
小学生がゲームばかりすることは、多くの家庭で直面する悩みです。
しかし「禁止」や「叱る」だけでは根本的な解決にはつながりません。
本記事でお伝えしたように、ゲームは使い方次第で教育的価値を持つツールにもなります。
大切なのは、子供の生活習慣や性格に合わせて、親子でルールを作り、良いバランスを保つことです。
特に重要なポイントは以下の通りです。
- ゲーム時間を減らすには、感情的にならず冷静に対応する
- 長期休みはスケジュール管理を徹底し、生活リズムを崩さない
- 時間制限アプリやペアレンタルコントロールで管理をサポートする
- 外遊びや運動など、他の楽しみを自然に取り入れる
- プログラミングや英語学習など教育的活用も視野に入れる
これらの方法を実践すれば、ゲームが「敵」ではなく、親子で共有できるポジティブな時間になります。
さらに、親が冷静に向き合う姿勢は、子供に自己管理や責任感を教える良い機会にもなります。
ゲームは現代の子供たちにとって避けられない存在ですが、それをどう扱うかは家庭次第です。
本記事の内容を参考に、ルールと工夫を取り入れてみてください。
きっと「ゲームばかりで困る」という状況から、「ゲームも勉強も楽しめる」生活へと変わっていくはずです。
親子で笑顔になれるゲームとの付き合い方を、今日から始めてみましょう。
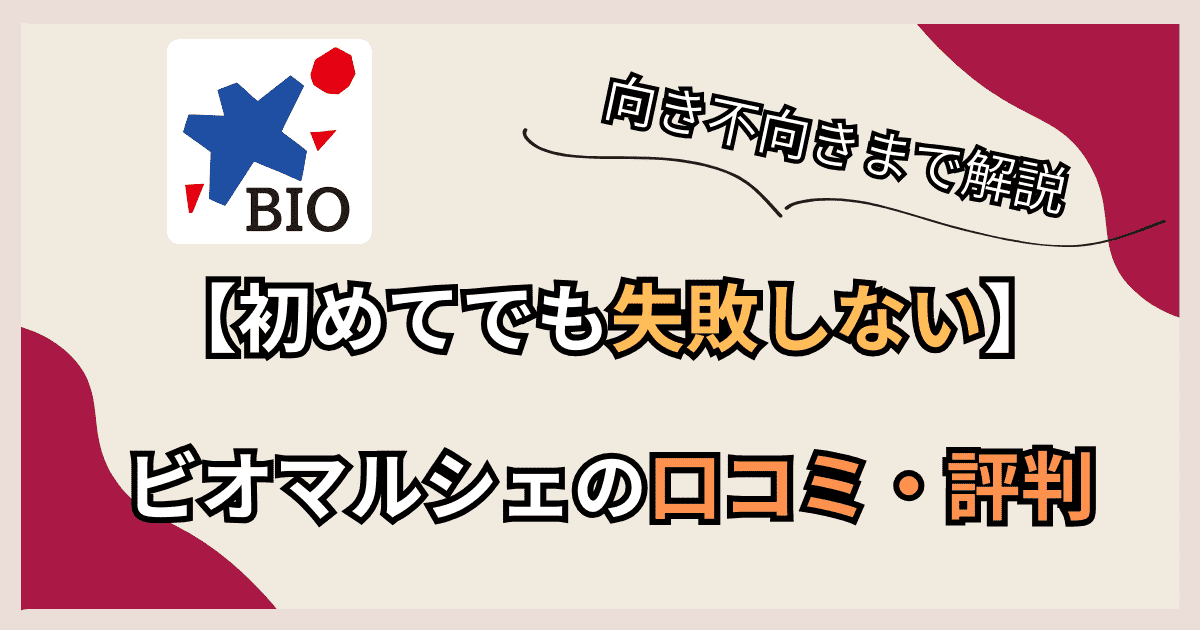
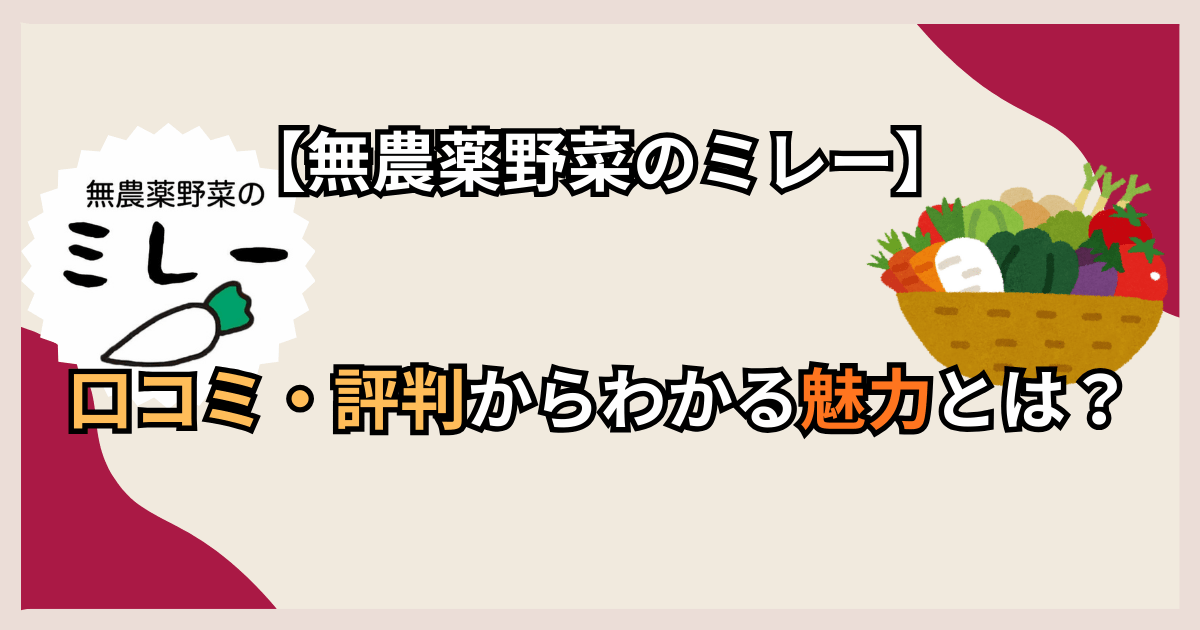
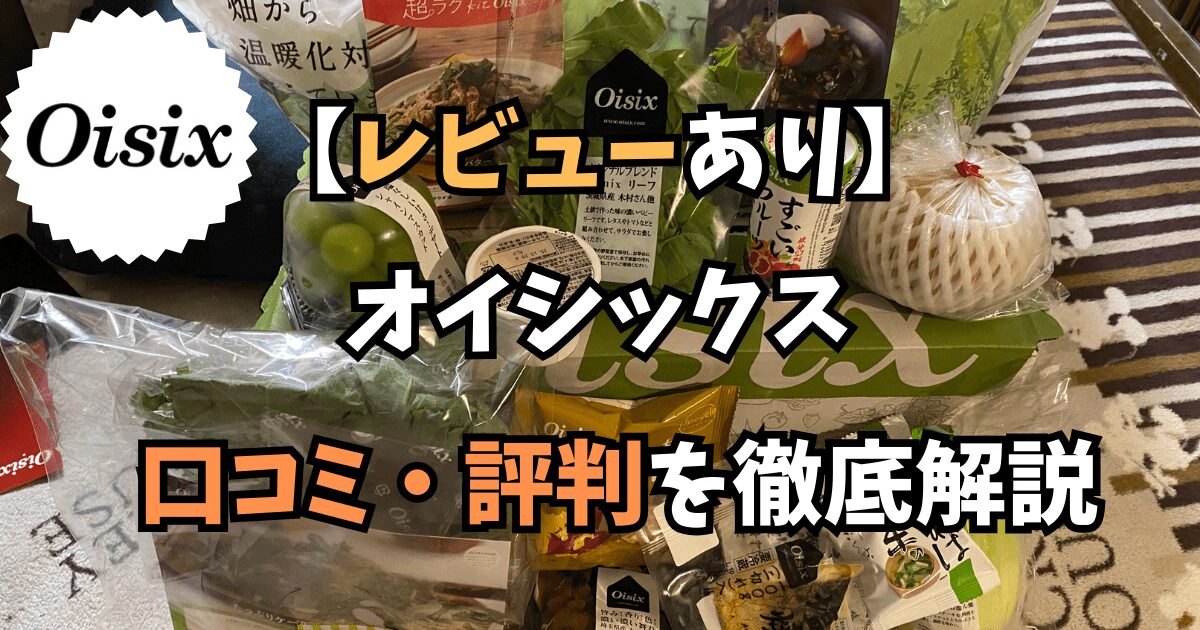
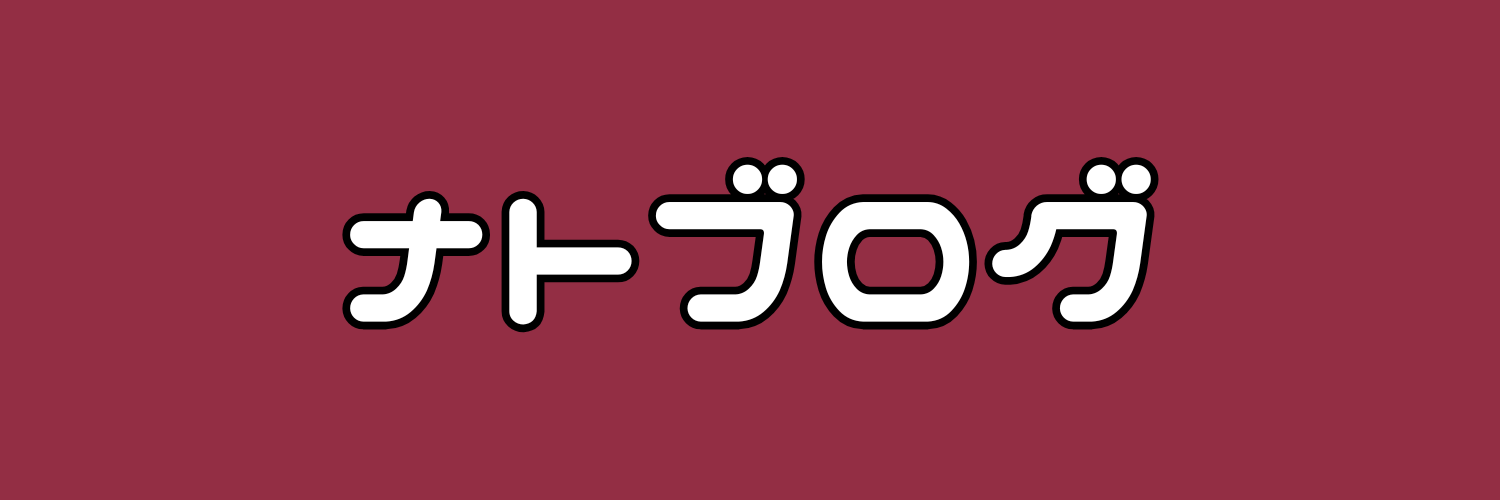
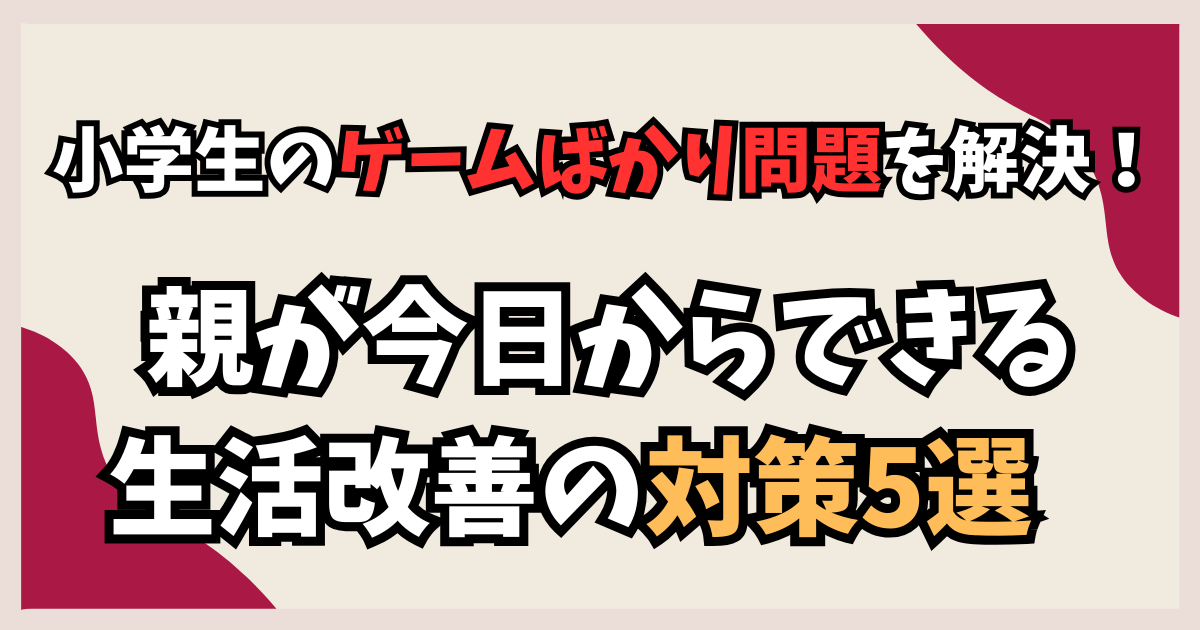
コメント