せっかく本を読んだのに「すぐに内容を忘れてしまう」「本の内容が記憶に残ってない」ということありますよね。
本を読んでも内容を忘れてしまったり、記憶に残ってないのでは意味がありません。
それを解決できる本が、樺沢紫苑さんが書かれたベストセラー「読んだら忘れない読書術」の新版!『読書脳』です。
著者の樺沢紫苑さんは精神科医であり作家。
樺沢心理学研究所を設立し、YouTube登録者46万人、メールマガジン12万人など累計100万人フォロワーに情報を発信しています。
著書45冊、累計発行部数230万部のベストセラー作家です。
そんな樺沢さんが書かれた読書についての本は「読んだら忘れない読書術」と新版の「読書脳」の2冊だけです。
せっかく読んだ本を忘れないように、「10年経っても忘れない読書術」を身につければ人生も変わるはずです!
それでは「読書脳」の内容を簡単にまとめていきます。
精神科医の読書術基本原則 3つの基本
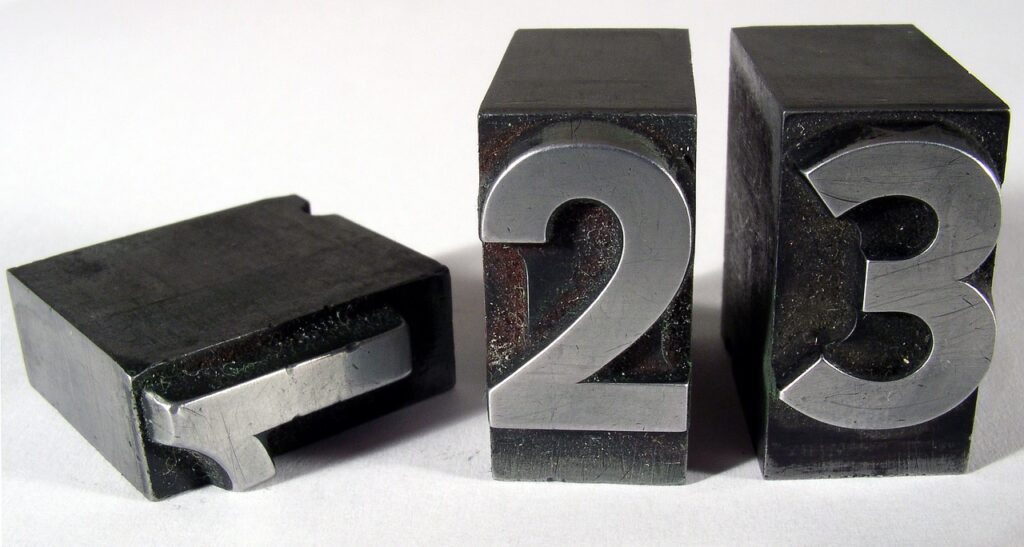
読書をする上で最も重要な柱、読書術の基本原則というべき「3つの基本」があります。
- アウトプット
- スキマ時間
- 「速読」より「深読」
アウトプット
いろいろな本で「1週間に3回アウトプットすると記憶に残る」と書かれています。
脳科学研究でも、最も効果的な記憶術として「最初のインプットから、7~10日以内に3~4回アウトプットする」ということが明らかになっています。
人間の脳は膨大な情報をすべて記憶することはできないので「重要な情報」以外は、全て忘れるようにできています。
脳が「重要な情報」と判断する基準は2つです。
「何度も利用される情報」と「心が動いた出来事」
・何度も利用される情報
膨大な情報は「海馬」という部分に仮保存されます。
その仮保存中に何度も引き出された情報は、「重要な情報」という付箋をつけ、「記憶の金庫」ともいうべき側頭葉に移動します。
「記憶の金庫」にうまく移動できれば「読んだら10年忘れない記憶」になります。
・心が動いた出来事
科学的なデータによって記憶力アップが確認されている脳内物質には、アドレナリン・ノルアドレナリン・ドーパミン・エンドルフィン・ドーパミン・オキシトシンなどがあります。
ワクワクした時に分泌するドーパミン
最高の幸福感に包まれたときに分泌するエンドルフィン
愛情やスキンシップに関連して分泌するオキシトシン
これらの脳内物質を読書中に分泌させることができれば、本の内容を明確に、長期間記憶することができます。
スキマ時間
ほとんどの会社員は、通勤時間、移動時間、約束の待ち時間などのスキマ時間合計すると、1日「2時間」近くあるはずです。1ヵ月だと60時間。
そのスキマ時間を60時間読書に使えば、読書スピードが遅い人でも、10冊読むことは可能です。
1日24時間のうち、断片化された時間を合わせれば2時間もあります。
これは、起きて行動している時間の約10%になります。つまり人生の1割はスキマ時間です。
この人生の1割に相当するスキマ時間を、「浪費」に使うか「自己投資」に使うかで、あなたの人生は変わります。
スキマ時間で本を読むときは「今日1日で読む!」という、目標設定をします。
目標設定は制限時間をつくることです。
制限時間を決めることによって、緊迫感が出るので集中力が高まり、記憶に関連する脳内物質が分泌され、記憶に残りやすくなります。
最初から1日1冊はハードルが高いので「3日で1冊」を目標にしてください。
「速読」より「深読」
「本を読んだ」の定義は「内容を説明できこと」「内容について議論できること」です。
感想や自分の意見を述べられなければ、本を読んでいる意味がありません。
感想や自分の意見を述べられないのは「アウトプットできない」ということです。
「アウトプットできない」ということは、自分の行動に影響を及ぼさないということです。
読書は「量より質」、「早く読む」より「きちんと読む」ことを重視してください。
最初に目指すべきは「読書の質」であり「読書のスピード」ではありません。
「読書の質」を十分に上げてから、その「質」を維持しつつ「より早く」を目指すべきです。
本から学びと気づきを得て、「議論できる水準」まで内容を理解するように、深く読む読み方を「深読(しんどく)」といいます。
「深読」は読書の必須条件です。「深読」できるようになってから「速読」「多読」を目指してください。
記憶に残る読書術 2つのキーワード
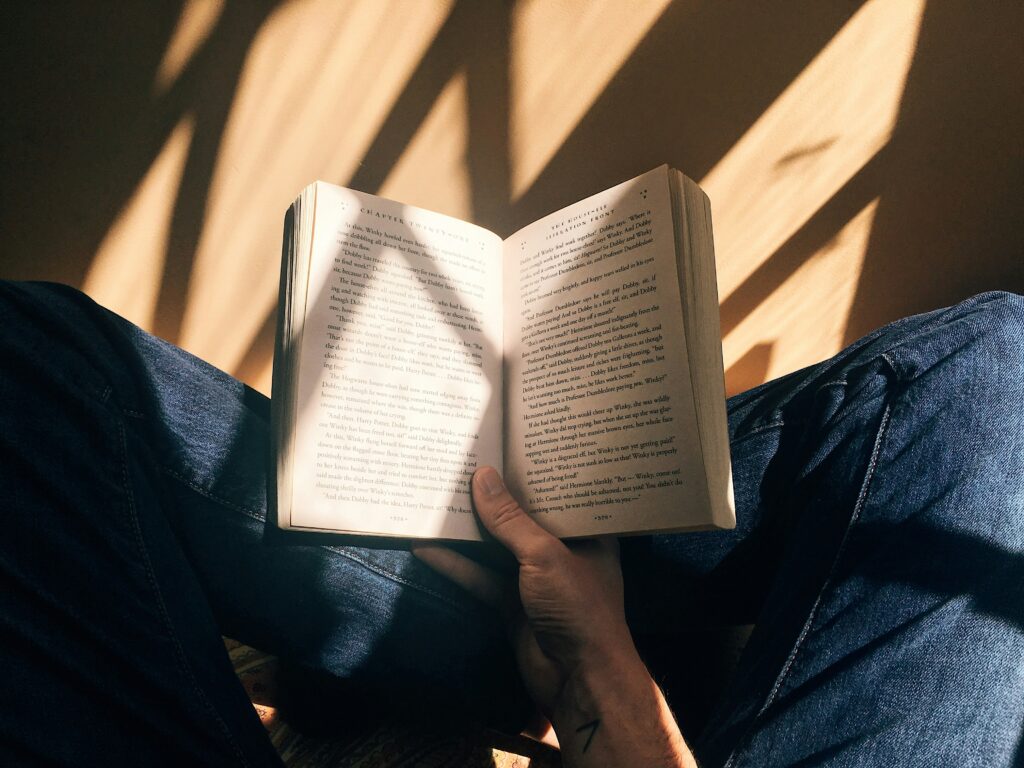
本書重要なテーマ「記憶に残る読書」「読んだら忘れない読書」ができるかです。
2つのテーマのキーワードは「アウトプット」と「スキマ時間」
この2つを意識するだけで「記憶に残る読書」ができるようになります。
アウトプット読書術
マーカー読書術
本を読むとき「綺麗に読む派の人」と「汚く読む派の人」に分かれると思います。
記憶に残し成長を最大化させるには、汚く読むことが必要不可欠です。
本を読むときに必要なツールは、蛍光マーカーとボールペンです。
本を読みながら気に入った一節や「気づき」の一節にラインを引きます。
実際に「気づき」や「疑問点」などを、本の余白にボールペンで書き込んでいきます。
必要に応じて付箋もあると便利です。
本を読みながらマーカーでラインを引くことで、インプットをしながら、最初のアウトプットを同時に行えます。
科学的には、ラインを引くことは間違いなく脳を活性化します。
マーカーでラインを引いたり、メモをしながら本を読むだけで、脳は何倍も活性化され、本の内容が記憶に残りやすくなります。
「自己成長につながる気づき」や「自己成長に役立ちそうな言葉」があれば、どんどんラインを引いたり書き込んでください。
テレビショッピング読書術
もっとも簡単なアウトプットは「話す」ことです。
「面白い」「ためになった」を連呼してもダメで、具体的にどこがためになったのか、本の内容を要約しながら相手に伝えることが重要です。
人に本を勧めるのに内容を思い出し、頭の中で整理しながら話さなければならないのでアウトプット効果は非常に高くなります。
本を読んだら1人だけではなく、複数に2度、3度紹介します。
複数の切り口で紹介するためには、複数の視点で読むことが必要になるので、本を深く読み込んでいく能力も養われます。
そうすることで「1週間に3回のアウトプット」も達成することもできます。
ソーシャル読書術
SNSでシェアをするとやらない場合に比べて何倍も記憶に残りやすくなります。
たった数行の感想を書くだけでも、本の内容を思い出す作業が頭の中で行われます。
つまり、「記憶の復習」が行われ、「3回のアウトプット」のうち1回がここで完了します。
感想を書くのが難しいと感じる人は、自分の心にい響いた1~2行を書き写し、自分のコメントもつける「名言投稿」でもいいです。
自分の投稿した「名言」は、ニュースフィードに流れ、タイムラインににも表示されるので、自分でも2度、3度は目にすることになり復習効果、記憶に残す効果は抜群です。
本を読んだら、ソーシャルメディアに「感想」や「名言」を投稿してみてください。
スキマ時間読書術
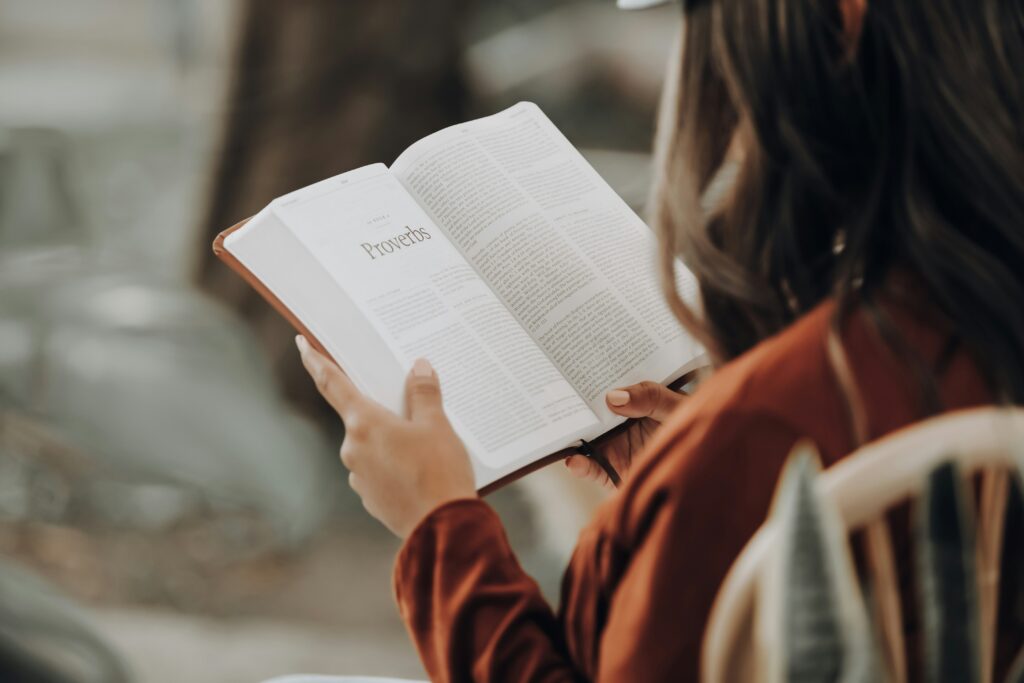
5分・5分読書術
何かの作業をするとき、集中力は、初めと終わりで特に強くなることが知られています。
心理学ではこの現象を「初頭努力」「終末努力」と呼ばれています。
単語の書かれたカードを連続して提示し記憶してもらう心理実験では、最初と最後の方に提示されたカードの正答率は高く、中間のカードは正答率が低くなるという結果が出ました。
最初と最後は集中力だけではなく、記憶力も高まるということです。
15分で本を読むと、「初頭努力」で5分、「終末努力」で5分、合計10分の「記憶力の高い状態での読書」が可能になります。
これを4回繰り返すと60分の中で40分も記憶力が高い状態で読書することができます。
一方で60分連続で読むと記憶力の高い時間は10分しかありません。
「15分程度のスキマ時間読書」の繰り返しでも、連続読書以上の効果が得られるというわけです。
15‐45‐90の法則読書術
誰にでも集中しやすい時間単位「15分」「45分」「90分」これをまとめて「15‐45‐90の法則」と言います。
高い集中力が維持できるのが15分。
普通の集中力が維持できるのが45分。
(授業、テレビドラマなどだいたい45分)
45分の間に、少し休憩を挟めば、90分の集中も可能。
(大学の講義、CMを抜いた2時間ドラマも実質90分)
「スキマ時間読書」において重要なのは「15分」です。
非常に高度な集中力を維持できる限界が「15分」です。
脳科学的に見ても15分という時間は、「極めて集中した仕事ができる時間のブロック」である、とされています。
このスキマ時間の15分で「読書」をするのか、スマホを触るのかで人生が変わってしまいます。
熟睡読書術
スキマ時間以外での、おすすめの時間帯は「寝る前」です。
寝ている間に新しいいインプットはされないので「記憶の衝突」が起こらず、頭の中で整理が進みます。
さらに、イギリスサセックス大学の研究では、読書を始めてわずか6分で、被験者たちの心拍数は落ち着き緊張感もほぐれたと言います。
その他のリラックス法と比べても、読書で最も高いリラックス効果が得られたと報告されています。
睡眠前の読書は、心と体をリラックスさせて、睡眠に入りやすくさせてくれるのです。
「読んだら忘れない」精神科医の読書術 超実践編
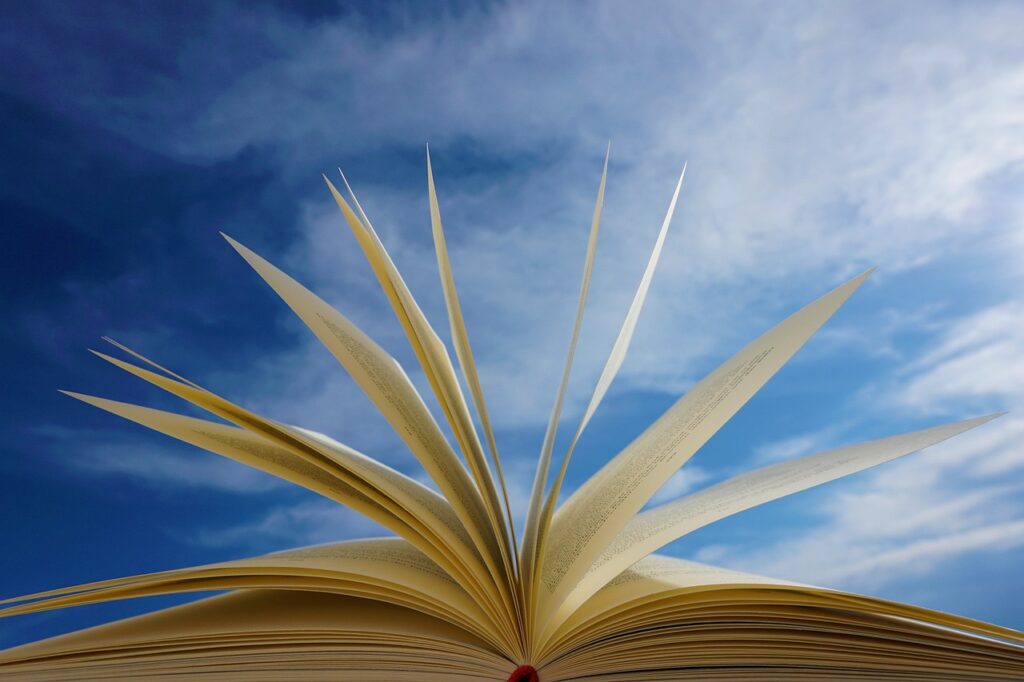
ここからは、記憶に残り、自分にとって役に立つ本当の読書をするための方法を紹介します。
パラパラ読書術
本を読むのは早い人は、全体をパラパラと見通して、全体を把握してから読み始める人が多いです。
最初にパラパラ読みをする3つの目的があります。
- 全体を把握する
- 本を読む目的を設定する
- 速読か精読かを決める
つまり本を読む前にゴール(目的地)と行く方法(読み方)を決めているわけです。
ワープ読書術
「この本で1番知りたいことは何か」を考えます
そして、その知りたい部分を先に読んでしまいます。
知りたいことが書いてあるのが何章なのか目星をつけて、結論が書かれていそうなところにワープします。
知りたいと感じたところ、深堀したいところ、疑問に感じたところがあれば、再度目次などで目星をつけそのページにワープして読んでいきます。
最初に「目的地」をだいたい把握しておくと、早く目的のページに到達することができます。
ワクワク読書術
「ワクワク感」に包まれて分泌される脳内物質が、幸福物質のドーパミン。
ドーパミンが分泌されると満足感、充実感、幸福感に包まれ、またその幸福感を再体験する為に同じことを欲求するようになります。
ドーパミンは、私たちのモチベーションを高めてくれる重要な物質であり、ドーパミンが分泌されることで記憶力も高まります。
鉄は熱いうちに打て読書術
「この本おもしろそう!」と興味がわいて本を買ったのに、忙しくて本を読む時間がなかった。
1週間たって改めて読もうと思っても、あまりワクワクしません。
1週間後には興味・関心が失われています。
つまりドーパミンが出ていないいないのです。
なので「面白そう!」と思って本を買ったら、買った直後からすぐ読み始めることです。
その日のうちかせいぜい次の日くらいまでには一気に読み終えてしまう。
そうすることで、ドーパミンが分泌された状態で本を読み切ることができ、強烈に記憶に残すことができます。
最後に
読書術の3つの基本原則
- アウトプット
- スキマ時間
- 「速読」より「深読」
そして2つのキーワード「アウトプット」と「スキマ時間」
実践編では4つの方法を紹介しました。
今回紹介しきれなかった読書術も本書では詳しく解説しています。
この本では読書術のほかにも、なぜ読書が必要なのか、電子書籍の活用方法、本の買い方なども詳しく紹介されています。
この1冊を読めば本を読む理由・本の選び方・読書術・電子書籍の活用が詳しく書いてあるので、選んで覚えるところまですべてが詰まっています。
読書をしてもすぐに忘れてしまう人におすすめの1冊です。
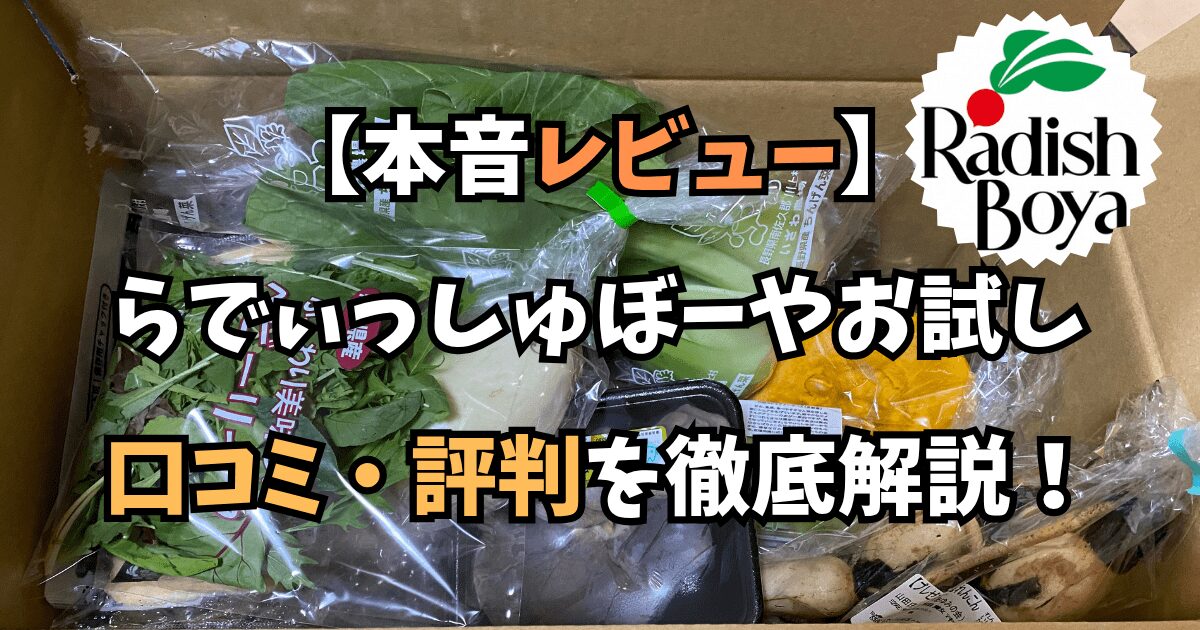
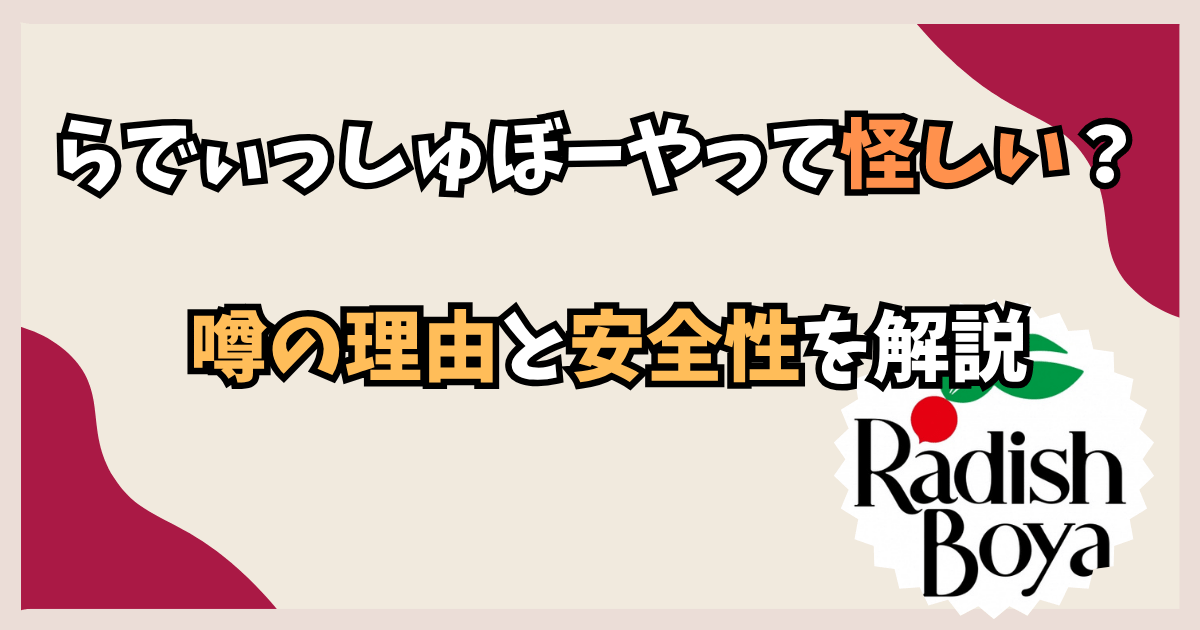
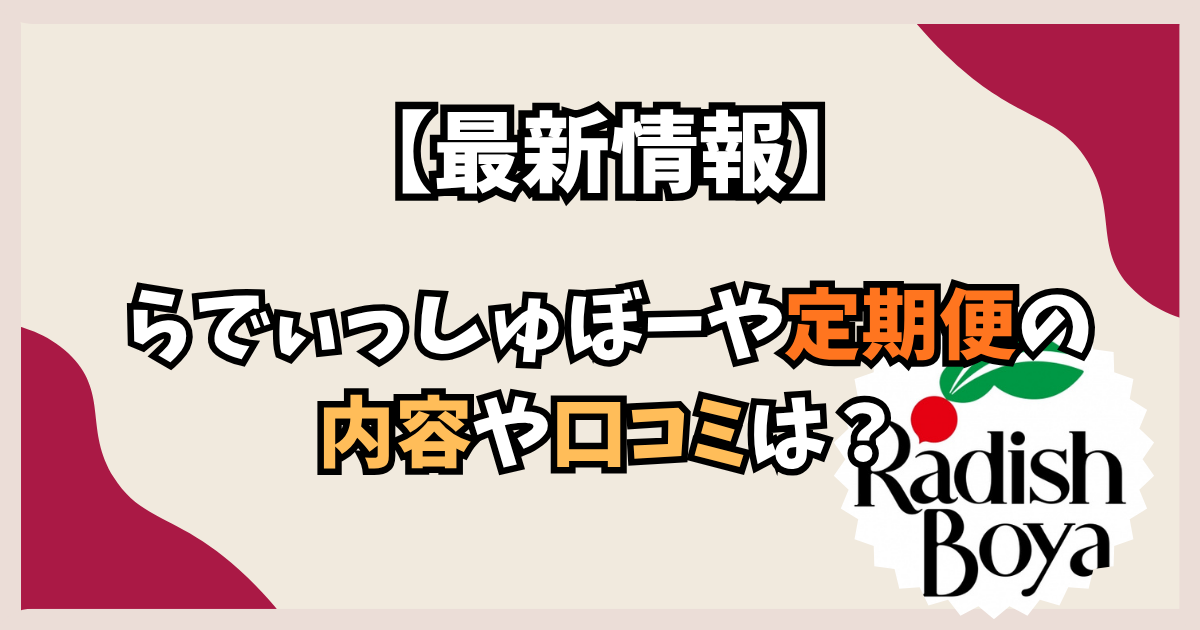
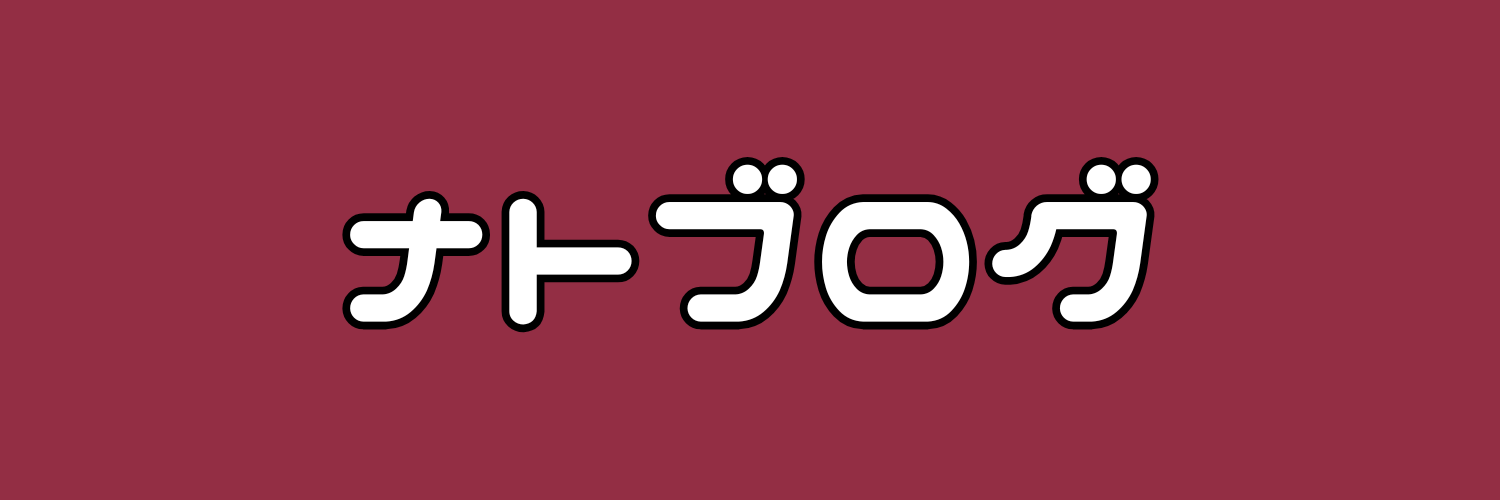
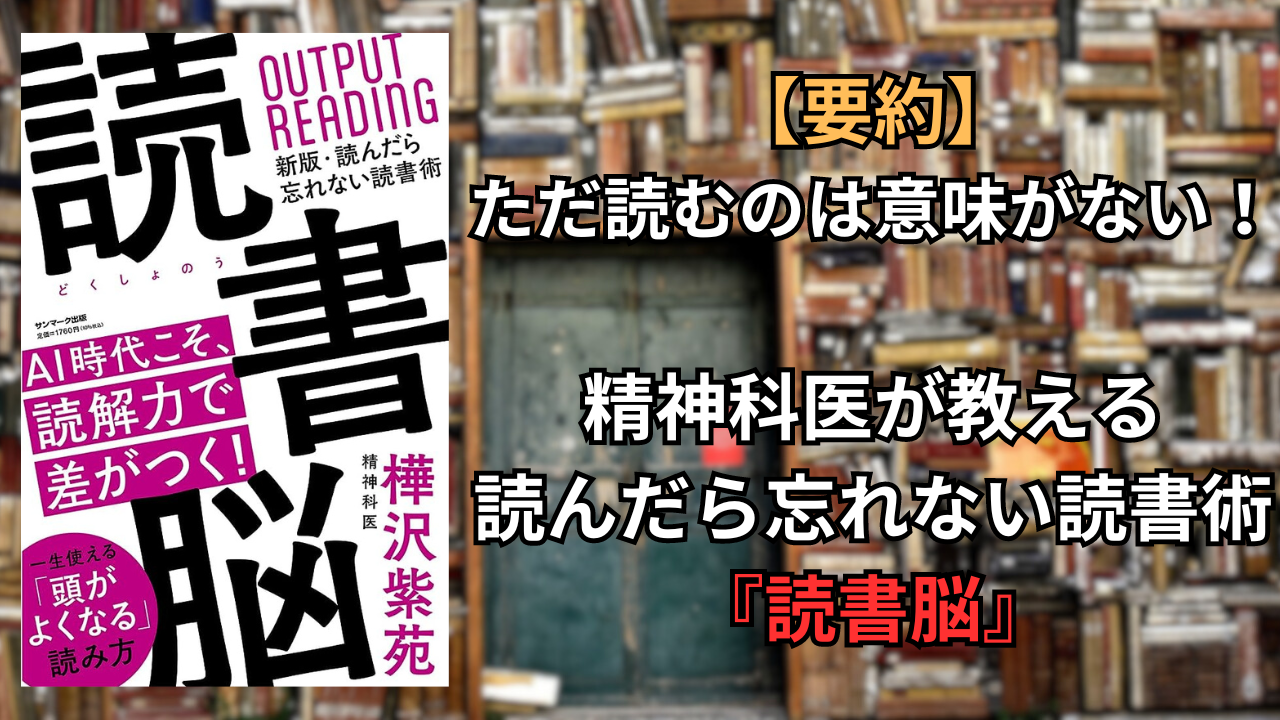
コメント