毎日忙しい中、子どもの栄養バランスなどを考えて作るごはん。
そんな思いとは裏腹に、子どもは野菜を食べてくれないことよくありますよね。
子どもには健康のために野菜を食べてもらいたいけど、
「なんで子どもは野菜を嫌うの?」
「野菜嫌いを克服させる方法がわからない」
「野菜嫌いを克服させた家庭はどうやったの?」
などの不安や悩みがでてくる方は少なくないと思います。
こちらのおすすめの健康本でも「野菜はいつもの2倍食べる」と野菜を重要視しています。
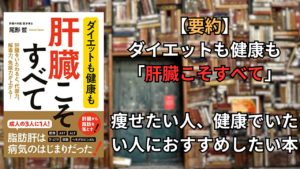
子どもの健康のためにも野菜を食べて良質な栄養を摂ってもらいたいですよね。
この記事では、
- 子どもが野菜を食べない理由
- 子供の野菜嫌いを克服する方法
- わが家で野菜嫌いを克服させるのに効果的だった方法
以上の3つについて解説していきます。
 ナト
ナト子どもたち2人ともピーマンとネギが苦手で食べられませんでした。
麺類に入っているネギはきれいに取り除かれ、細かく刻んでもピーマンの入ったものは口をつけない、などの徹底ぶりでした(笑)
ですが、今ではネギもピーマンも食べられるようになっています。
野菜栽培キッドでの家庭菜園で、子どもたちの野菜嫌いを興味に変えてあげることおすすめです。
子供が野菜を嫌いになり食べない理由とは?
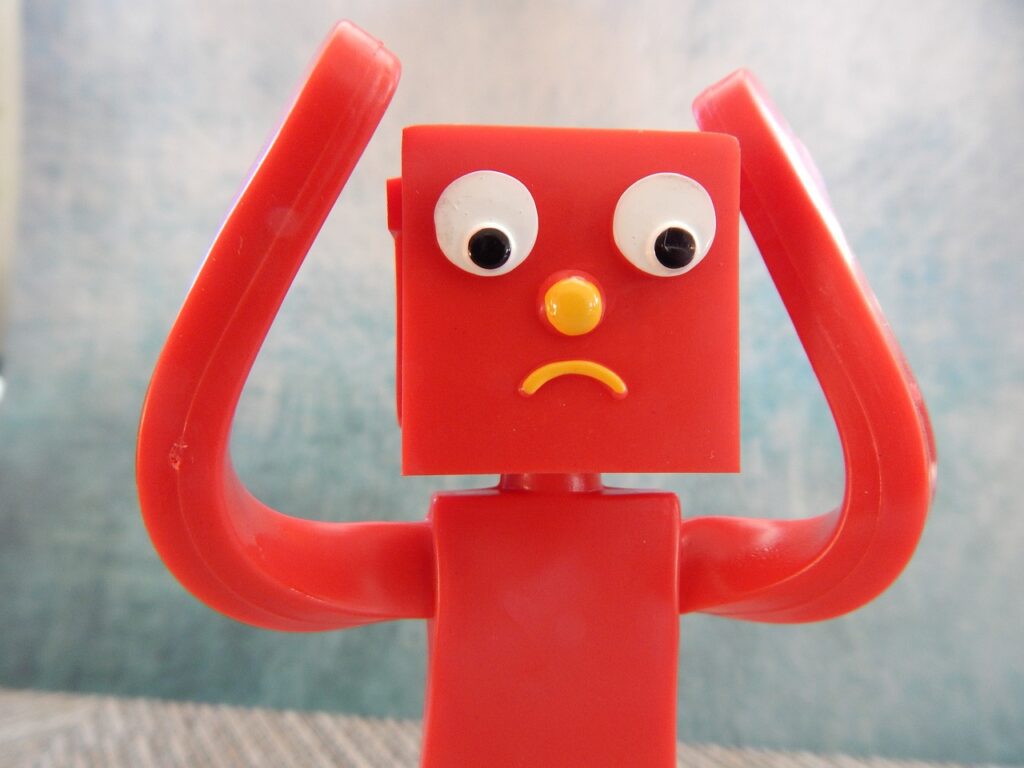
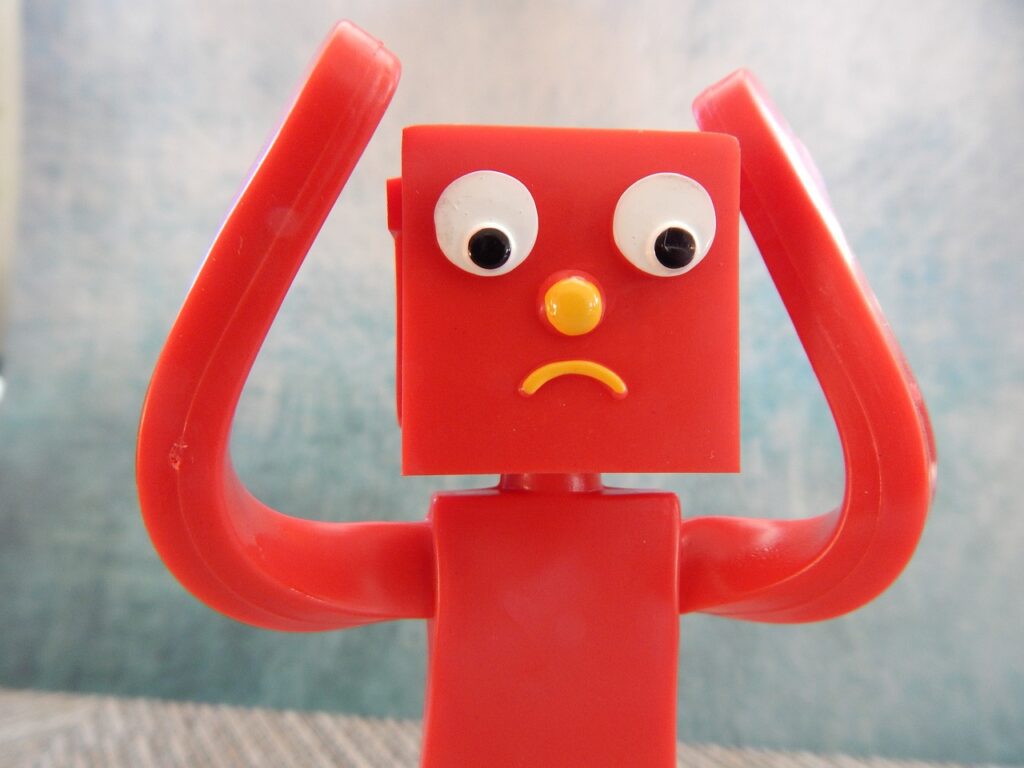
子どもが野菜嫌いで、食べない理由には以下のことがあげられます。
- 味やにおい好み
- 見た目や食感
- 過去の経験
- 家庭の食習慣
以上の4つのことが、子どもが野菜を食べない理由になります。
子供が野菜を嫌いになる要因


なぜ、先ほどの「子どもが野菜を食べない理由」から、子どもたちは野菜を食べなくなってしまうのか。
ここでは、その要因となる理由をひとつずつ解説していきます。
味やにおいの好み
多くの子どもは甘い味を好むため、野菜の自然な苦味や酸味を嫌うことがあります。
子どもは大人よりも味に敏感です。
甘い味はエネルギー源(糖分)として好まれますが、苦味は毒性の可能性があると思い嫌う傾向があります。
ほとんどの野菜には苦味や辛みが含まれていて、子どもはこの苦みや辛みに敏感になります。
特にピーマン・セロリ・パセリ・ゴーヤ・ネギなどが苦手な子どもが多いです。
特定の野菜には独特の風味があり、これが嫌いな子どももいます。
青臭さのある野菜も子どもは苦手なことが多い傾向にあります。
特にピーマン・春菊・ブロッコリーなどが苦手な子どもが多いです。
見た目や食感
野菜には子どもが嫌う食感や見た目をしたものがあります。
子どもが嫌いな食感には、かたい・しなびた・ぬめり・繊維質の多い食べ物などが嫌われがちです。
にんじんやセロリなど、かたい野菜は噛むことが難しく嫌がることがあります。
オクラやほうれん草のようにぬめりがある野菜も不快に感じることがあります。
アスパラガスなど、繊維質の多い野菜は子どもにとって食べにくい食材です。
子どもは初めての野菜を見たとき、色や見た目から食べられる物か判断します。
特にニンジン・カボチャ・トマトなどの色の濃い緑黄色野菜は、苦手な子どもが多いです。
過去の経験
子どもは過去に野菜で嫌な思いをしてしまうと、嫌いになってしまいます。
たとえば、「まずかった」「吐き気がした」「無理やり食べさせられた」などの嫌な記憶が残り、再び食べるのを拒むことがあります。
一度でも食べてみて嫌いだと思った場合、その後も同じ野菜を食べようとしなくなることがあります。
さらに、一度嫌いになった野菜に似た形やにおい・色の野菜も警戒して食べなくなってしまうことがあります。
家庭の食習慣
家庭での食事の習慣や親の食事の好みが影響することがあります。
親が野菜をあまり食べなかったり、嫌いな野菜を入れない場合、子どもも同じように野菜を嫌う傾向が強いです。
家庭で調理法のレパートリーが少ないと、子どもが特定の調理法では野菜を嫌がることがあります。
たとえば、野菜を楽しく調理する・子どもが興味を持つ形に切る・他の好きな食材と一緒に調理するなどの工夫がないと、子どもが野菜を食べなくなってしまうこともあります。
子供が野菜を食べないとどうなる?


では、子どもが野菜を食べないとどうなってしまうのか。
子どもの時に野菜が嫌いでも、成長とともに野菜を食べるようになっていきます。
しかし、子どもの成長時期に野菜を食べないと健康上の問題や栄養不足が発生する可能性があります。
野菜は子どもの成長に重要なビタミンやミネラル(鉄分、カルシウム、カリウム、マグネシウム)を豊富に含んでいます。
ビタミン不足による、免疫力の低下・皮膚や視力の問題などが発生する可能性やミネラル不足よる、貧血・骨の健康問題・筋肉の機能低下などが発生する可能性があります。
さらに、野菜には食物繊維が多く含まれており、消化器系の健康を維持するために重要な働きをします。
食物繊維が不足すると、便秘や腸内環境の悪化が起こりやすくなります。
野菜は低カロリーで栄養価が高いものが多く、エネルギー源としても重要です。
野菜を食べないと、他の高カロリー低栄養の食べ物に頼りがちになり、不健康な食習慣が身につく可能性や健康な体の維持が難しくなります。
もちろん、野菜を食べた方が栄養バランスがとりやすいです。
ですが、ほかの食べ物から栄養を摂れていれば、心配する必要はありません。
「残さず食べなさい」など、無理に食べさせようとすると恐怖心や苦手意識が強くなってしまうので、できる範囲で食べさせるのが良いです。
楽しく子供の野菜嫌いを克服する方法


子どもの野菜嫌いを克服させるには、視覚(見る)、聴覚(聴く)、味覚(味わう)、嗅覚(嗅ぐ)の五感で楽しませることが重要です。
そうすることで、野菜に感じていたネガティブな印象を、ポジティブにとらえることができるので、野菜嫌いを克服するきっかけになります。
子供が野菜を食べるようになる工夫とは?


野菜嫌いを克服させるには、苦手意識を取り除くことが重要です。
まずは、「味が嫌い」「見た目が嫌い」「匂いが嫌い」などのネガティブな印象を変えていかなくてはいけません。
野菜を細かくする・すりおろ・柔らかくなど調理法を変えたり、星・ハート・動物の形に切り、子どもたちを楽しませながら克服させる方法が効果的です。
さらに、味付けで子どもが苦手な野菜の味を変えていくのも良いです。
大変ではありますが、そういった細かい工夫で子どもたちは苦手意識がなくなり、食べられるようになっていきます。
子どもたちの野菜嫌いを克服するのに効果抜群だった方法


毎日献立を考えるだけでも大変なのに、子どもに野菜を食べてもらえるように調理していたら時間が無くなりますよね。
苦手意識や抵抗感が強いと「実際に試したけど全然食べてもらえない」ということもあります。



わが家では、実際に調理法を変えて食べてもらおうとしましたが、食べてもらえませんでした。
そんな野菜嫌いの子どもたちに効果的だったのは「野菜づくり体験」でした。
野菜づくりを体験することで、野菜への興味・関心が湧き苦手意識がなくなって「食べてみたい」に変わります。
カゴメ野菜定点調査では野菜を植える、育てる、収穫する、食べる、触れる、学ぶ、調理する、加工するといった、野菜に関する体験が多い人ほど野菜への好意や知識、関心度が高いことがわかっています。


家庭菜園は数千円ほどで簡単に始められ、子どもの野菜嫌いを克服できて、節約にもなります。
今年育てた野菜は、ナス・ピーマン・大葉・小玉スイカ・トウガラシ・トマトの6種類を栽培しました。




だんだんと大きくなっていくのを、子どもたちと水やりをしながら見ています。
プランターでの栽培なので、子どもの夏休みの自由研究などにも使えます。
初心者の方は、簡単にできる栽培キットがおすすめです。
まずは小さく始めて、子どもに楽しんでもらうところから始めてみてください。
最後に
いかがでしたか?
子どもの野菜嫌いは今も昔も変わらず起こる問題です。
わが子の、健康や成長を願って料理をしているのに食べてもらえないと、ショックも受けますよね。
子どもたちの野菜嫌いを克服するには、調理法も大切ですが野菜への苦手意識を取ることが大切です。
子どもたちと一緒に野菜栽培をすることで、野菜に興味・関心が湧きます。
野菜嫌いを克服する第一歩として、野菜栽培を始めてみませんか?
やってみると意外と楽しいので、是非試してみてください。
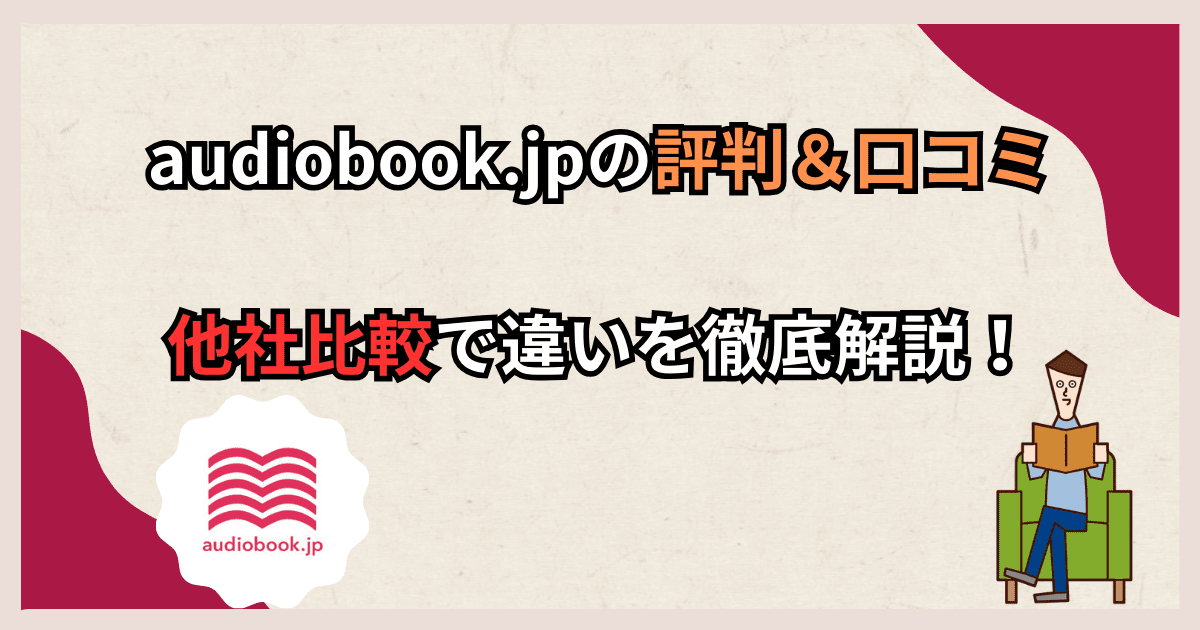
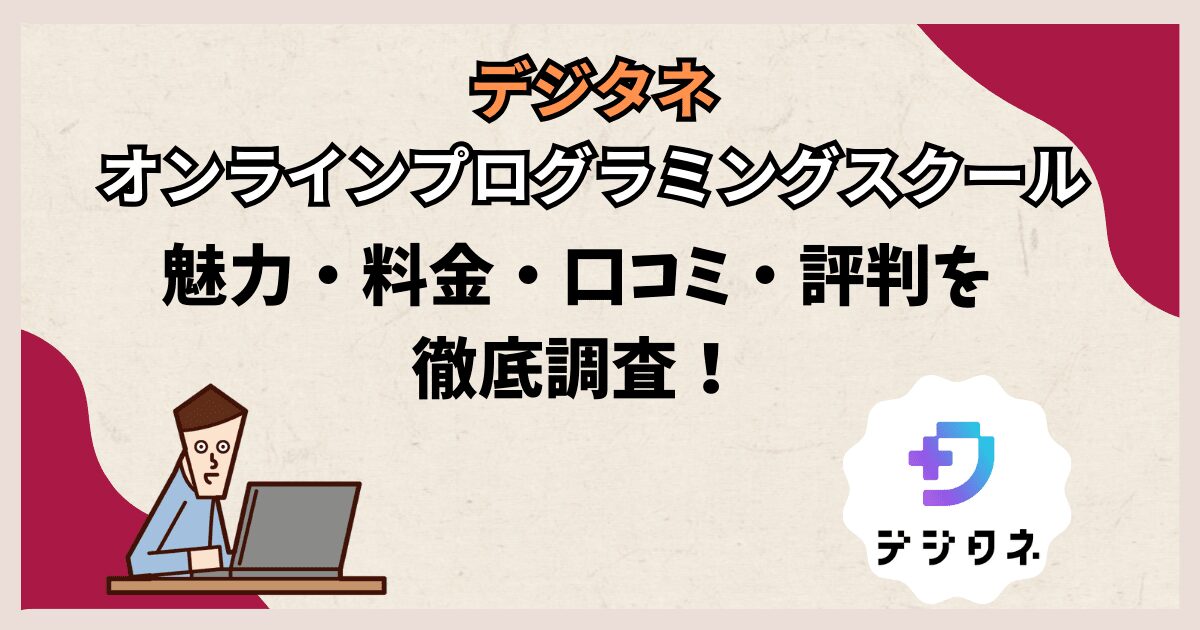
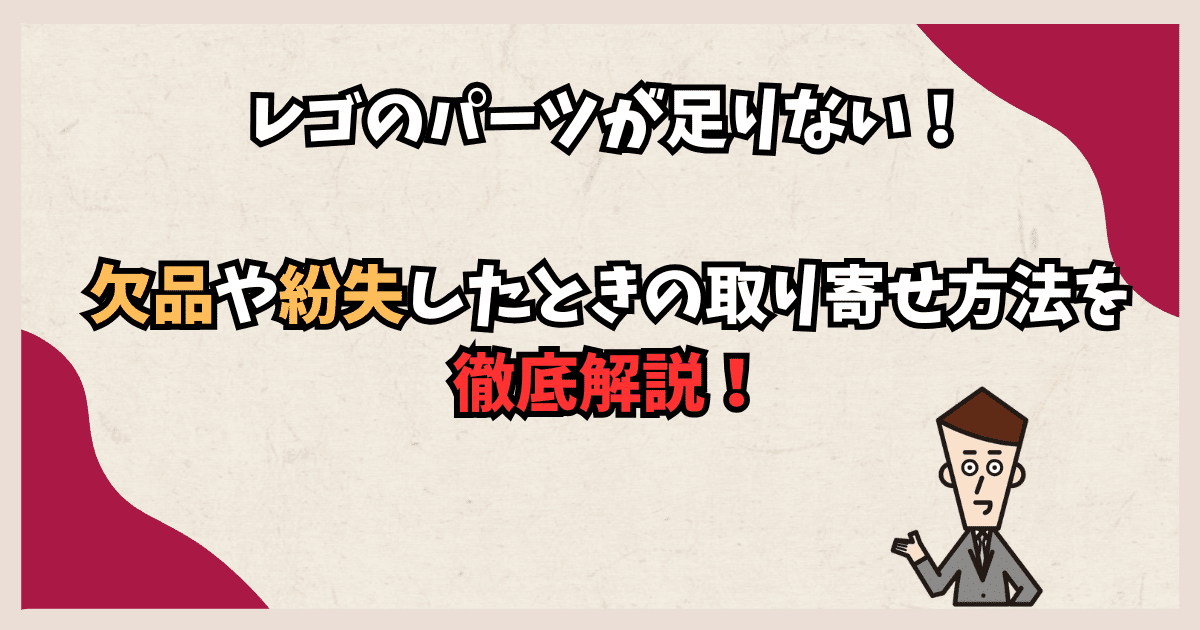

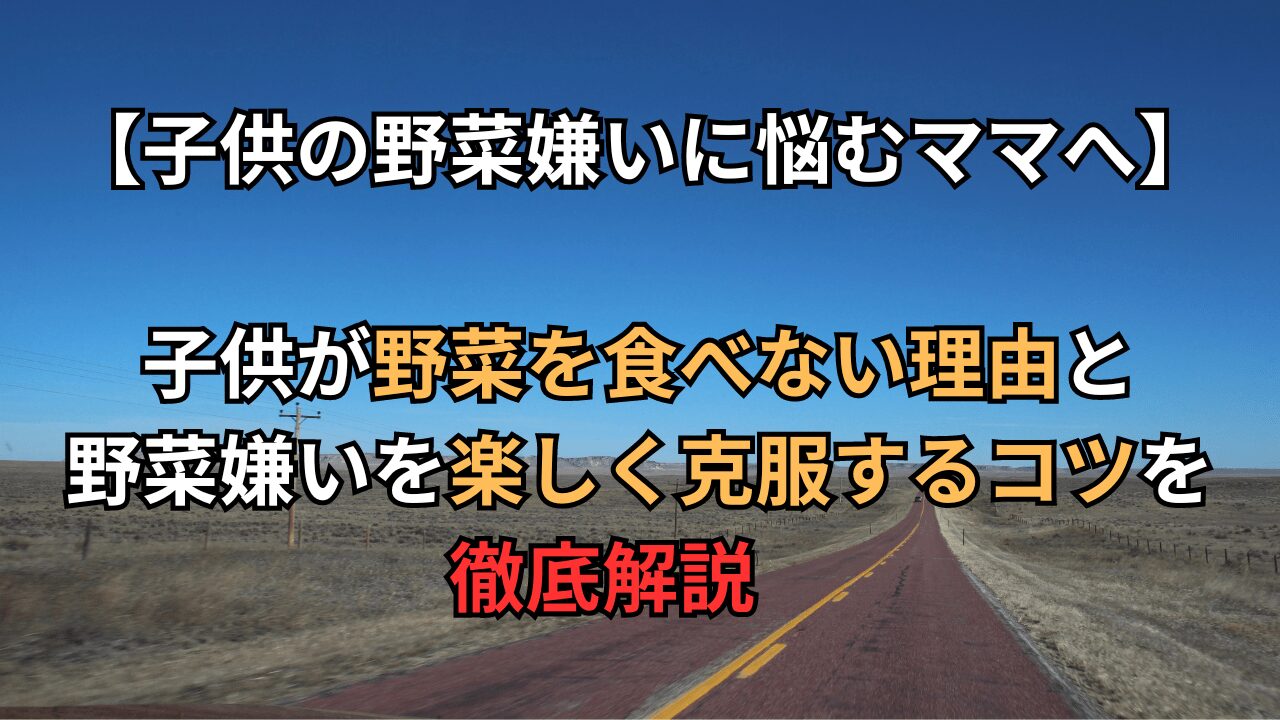
コメント