子育てをしていると絶対に「悩み」が出てくると思います。
その悩みの中で「子どもが話を聞いてくれない」「反抗期の子どもにどう話しかけたらいいかわからない」「親子関係が良くない」など様々な場面で、子どもにどう「言葉かけ」していいかわからないときがありませんか?
 ナト
ナト子育てをしていると、子どもへの「言葉かけ」には結構悩みますよね。
やはり「言葉かけ」1つで子どももかなり変わったりするので、悪い方向にいかないように慎重に言葉は選ばなければなりません。
そんな時どう伝えたらいいのかを知りたいですよね。
今回は、そんな「言葉かけ」をアドラーの心理学×幸福学から学べる本「子どもが一瞬で変わる『言葉かけ』」を紹介します。
著者は平本あきおさんと前野隆司さんの2人です。
平本あきおさんは米国アドラー大学院修士号獲得。世界中のカウンセリング、コーチング、瞑想を統合し、包括的で再現性のあるオリジナルメソッドを開発。
産業、医療福祉、教育、政治、スポーツ、芸能など各業界のリーダーや起業家もサポートし約10万人の研修実績を誇ります。
前田隆司さんは、ロボット工学に関連した人工知能の研究途上で、人間の意識に関する仮説「受動意識仮説」を見いだします。
現在は、ヒューマンインターフェイス、ロボット、教育、地域社会、ビジネス、幸福な人生、平和な人生のデザインまで、様々なシステムデザイン・マネジメント研究を行っています。
アドラー心理学のエキスパートと幸福学の第一人者の2人がアドラー心理学と幸福学から「言葉かけ」を教えてくれます。
この本では、子どもも親も楽になる34の声かけ具体例と考え方が書いてあるので、ほとんどの言葉かけの悩みはこの一冊で解決できます。
様々な状況や場面で使える言葉がけが学べるのでかなり気持ちが楽になります。
興味ある方はや要約無しで自分で読みたい方は、ぜひ本書を読んでみて参考にしてみてください。


意思決定が幸せを方向づける


アドラーの観点から言うと、2人以上の人間が集団となった時に、意思決定の方法は3つあります。
①話し合って決定(民主主義型)
お互いが話し合って方向を決める関係
②誰かが決定(独裁型)
誰かがリーダー、ボスになり「俺の言うことを聞け」と指示・命令する関係
③誰も遠慮して決まらない(アナーキー型)
家族という集団も、このどれかに当てはまります。
決定する内容や状況によって違うケースもありますが、「すべて母親が決めている」「家族で相談はするが、最終的に父親が決めている」「父親が指示・命令を出すが、実は決めているのは母親」「常に家族で相談して決めている」など、それぞれの家庭ならではの傾向があります。
実は、現代の日本社会では、知らず知らずのうちに③のパターンにを身につけてしまっている人が多いのではないでしょうか。
言いたいことが言えない、やりたいことがやれない、顔色をうかがって我慢してしまう。そんなパターンです。
アドラーは「その家庭の子どもはパターンを受け継ぐ」と考えました。
ただし、大人になる過程で学習する機会がある場合は、パターンを抜け出すことができると言います。
子どもは、自分の意見をテーブルに出して、尊重してもらえる、話し合いながら決めていくことでお互いに協力できる関係を家庭で経験しておくほうが「意思決定」に慣れた子どもが育つので学校や社会にでてからもうまくいきます。
その方が子どもにとっても幸せではないでしょうか?
親子で幸せになるための4ステップ


大人もまた人間的に成長できるのが、アドラー流子育ての良さのひとつだと言えます。
子どもを思い、子育てに向き合う中で、大人も成長し幸せになれる、そんなことをイメージしながら4つのステップ考えてみました。
イライラしたり、失敗してしまったとしても、自分を責めずに自分自身を認めてあげる。
親が自分のダメなところを受け入れられると、子どものダメなところがあっても「そういうところがあっても好きだよ」と受け入れられるようになる。
「今どうしたいと思ってる?」「なぜこれをやりたくないのかな?」と子どもの目線で問いかけながら、子どもが「何をどうしたいと思っているのか」を理解しようとする。
「何をやりたいか」「どうしたらできそうか」「自分らしいやり方は?」などを問いかけながら、未来から逆算できるようにサポートする。
「幸せに生きる術」は、何歳になってからでも学んで習得することができます。
「子どもに幸せになってほしい」と願うなら、親や先生など、周りの大人も「自分も絶対に幸せになる!」とコミットして欲しいのです。
現代アドラー心理学の土台となっていいるのが「共同体感覚」です。それを構成する要素が「自己受容・他者信頼・貢献感」の3つです。
お母さんは「自分をねぎらう」「自分を責めない」ということが必要になります。
それは「幸福感は伝染する」という研究があるからです。
両親が幸せで仲がいいと、子どもも幸せな人生を送る可能性が高いという研究結果があります。
重要なポイントは、子育てをするうえで一番大事にしてほしいのは、保護者や先生自身の「幸福」です。
人間の幸福度が高まる4つのポイント「幸せの4団子」で幸福を感じれます。
幸福の4団子を詳しく知りたい方はこちらの書籍の「幸せをつくる4要素」で詳しく書かれています。


「しつけ」とはいったい何なのか


お母さんと子どもの関係で最初に向き合わなければならない課題が「しつけ」なのかもしれません。
常識にとらわれすぎずに、自分らしい子育てをしたいと思っていても、思い通りにいかないのが子育てです。
では、「しつけ」とは何を、何のために子どもに教えようとするものなのか。
アドラーの心理学でよく使われる例を挙げてみます。
大人たちが食事を取っているときに、子どもが大声で騒いだり遊び始めたりした場合です。
そんな時、親は上から目線で「お行儀が悪い」「みっともない!」「いい年して恥ずかしいでしょ」「お兄ちゃんなんだから静かに」といった言葉で叱るかもしれません。
あるいは、子どもの代わりに謝ったりしてしまうこともあるかもしれません。
アドラーの心理学では「自分の責任が取れる範囲で自由にする権利がある」という考え方をベースにしつけをします。
まず「大人は静かに食事をする権利があります。そして、静かにできるなら子どもも食卓に一緒にいて良いよ」と伝えるのが、しつけの第一歩です。
「騒ぐのをやめて静かに過ごせたら、大人と一緒にいる権利がある」一方で、「騒ぎ続ける」なら、自由にやれる範囲が減っていくということになります。
これを理解し、自分で選んで振る舞えるように導くことが「しつけ」です。
アドラーの言う「しつけ」は「上から目線のマウント」とは全く違います。
電車内で子どもが騒いでしまうのは、他の人の迷惑になることがわかっていないからかもしれません。
それを教えるのが大人の役目です。
電車を利用するという自由のために、周りの人の居心地も大切にできるようになることが「しつけ」の目的です。
しつけの3ステップ


以下は、小学校教師のアドバイザー梶谷希美さんが、アドラー心理学をベースにつくった「しつけ」のステップです。
子どもにまず教えるべきなのは、自分と周りの人を尊重すること。
そして、その態度によって自分の周囲の人が、お互いに「安心と安全を感じられる居場所」にしていくことができることを学んでいきます。
子どもが社会にでて、自分らしい人生を生きつつ、他人の力を借りながら生きていくための力を持ってもらいことが重要です。つまり、自立と協力ができるようにサポートします。
理由や改善法を自分で考えられるように、質問やヒントを伝えると良いです。
「人から愛される人」「人から応援される人」になれるようにサポートします。
「ちゃんとした姿勢で聞いてもらった方が相手は嬉しいし、あなたに対して好感を持つ」「身なりを整えた方が気持ちがいいし、周囲の人も同じだよ」ということは、教えてあげないと子どもはわかりません。
上から目線で伝えるだけでなく、理由までしっかり説明しましょう。
「ヨコから」言葉をかける


困った行動をする子どもはまだ分別がついていません。
そんな子どもに「好き勝手やっていいよ」というと、ものが壊れたり、ケガをしたなどのアクシデントが起きて子どもは叱られ、大人同士も責め合ってしまいます。
だからと言って、厳しくして子どもに嫌われたくないから強くも出られない、という中途半端な態度を取ってしまい、状況が悪化するケースもあります。
そうならないためにどうしたらいいのかのヒントが「ヨコの関係」なのです。
アドラー的に言うなら「1ミリも上からではなく、1ミリも仕立てに出ない」というスタンスを取ることが大事です。
上からでも下からでもないスタンスを子どもに見せることで、子どもは相手が1人の人間として見てくれていることを感じ取り、紳士・淑女的に答えざるを得なくなります。
ヨコの関係のキーワードになるのが「あなたはどうしたい?」という問いかけです。
自分自身で自分を探求していくことが「自立」への第一歩です。
アドラーは「反抗期」という時期を「自立期」としてとらえています。
相手に単に関心を向けて叱るのではなく「相手の関心」そのものに関心を向けて「本当はどうしたいのか?」「その行動にはどういう理由があるのか?」と、大人に接するように「ヨコの関係」で接すると、子どもも反抗する代わりに「本当はこうしたかった」ということを少しずつ話してくれるようになります。
「悪いとわかっているいるのに何度も繰り返す」場合には、子どもの気持ちをゆっくり聞いてあげる必要があります。
叱ることも必要なこと
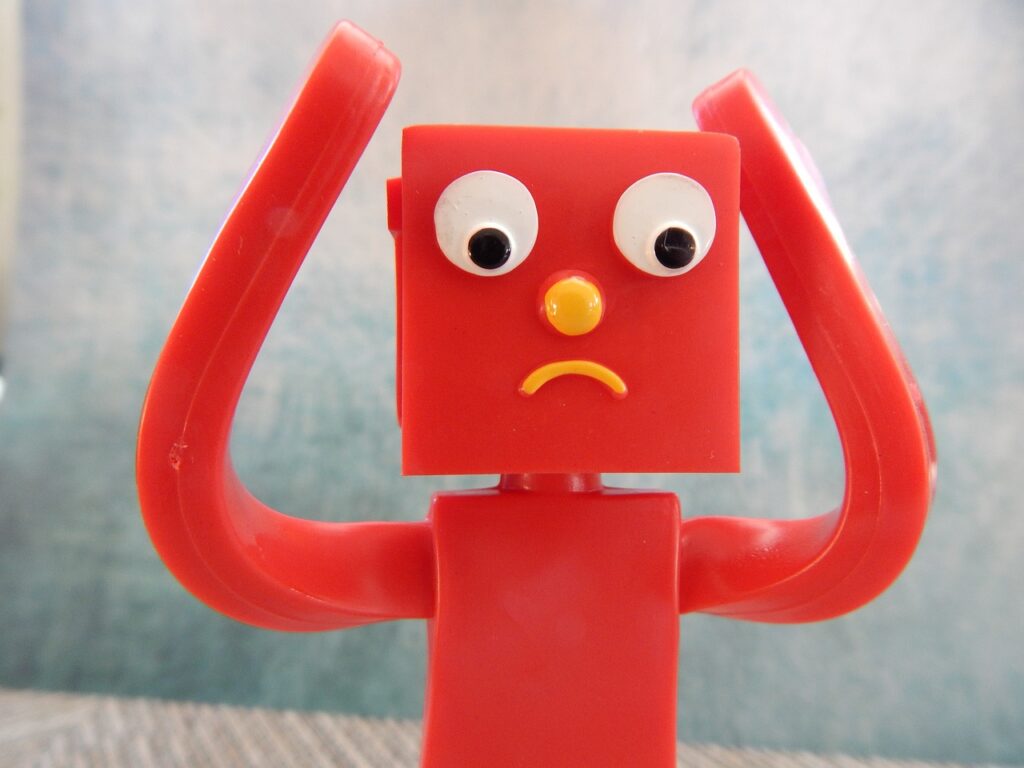
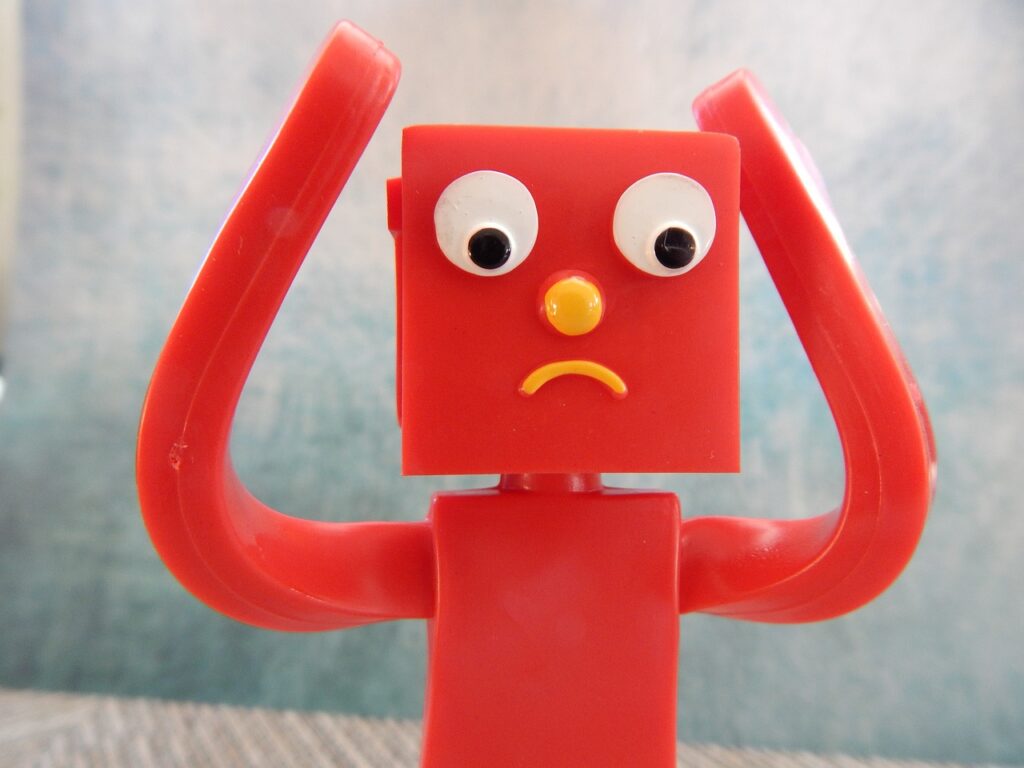
アドラーは「フラットなヨコの関係がもっとも大切だ」と言いますが、絶対に叱ってはいけない、ということではありません。
幸福学からみても、アドラーの叱るでもなく褒めるでもなく「勇気づける」ことが大事なのだという考え方は、とても共感できる内容だそうです。
でもそれは「叱ってはいけない」という意味ではありません。
場合によっては勇気づけるために「本気で叱る」ことも必要になってきます。
その時に大人は、ただ感情に任せて怒るのではなく、「なぜ叱っているのか」についての理由を自分自身で理解していなくてはなりません。
子どもの不適切な行動のには4つの目的があります。
子どもの目的:①注意を引く➡②権力闘争➡③復習➡④無気力で示す
親・大人の感情:①やっかい➡②腹が立つ➡③傷つく➡④あきらめる
これに対処する方法がこちら。
ステップ1:不適切な行動に注目しない。
ステップ2:適切な行動に注目する。
ステップ3:適切な行動をしているほかの子どもに注目する。
適切な行動とは、普段の生活で子どもが何気なくやっている当たり前のことを通じて、「悪いことをしないほうが注目してもらえる」というメッセージを伝えます。
子どもが何も話してくれないとき


一般的に「相手が何も話してくれない」場合には3通りのパターンがあります。
- 話したい相手ではないから
- 今は話したくないから
- どう答えたらいいかわからないから
もし、心理的な抵抗がある場合は、その相手が「心理的安全性」を感じられるように、信頼関係を築く必要があります。
すぐに話してほしいと思うのは、お母さん自身の不安を解消したいからで、お母さん自身があせっているからかもしれません。
すぐに結果を出そうとあせらなくてもいいのです。
ゆっくり子どものペースに任せて話したくなるのを待ってあげてください。
もう一つ、結構ありがちなのが「スマホ」です。
とにかく忙しくてなんでも「ながら」になってしまいがちな生活ですが、時にはせめてスマホをしまって、子どもとの一緒に過ごす時間を作ってみましょう。
「子どもに関心を持つ」よりも「子どもの関心」に関心を持つことが、一緒に過ごすときのポイントです。
子どもの関心に関心を持つことは、信頼関係を築いていく第一歩です。
最後に
いかがでしたか?
みなさんにも当てはまるところがあって共感できたのではないでしょうか。



僕がこの本を読んで一番刺さった言葉は「子どもの関心に関心を持つ」という言葉です。
今まで「子どもに関心を持つ」ことが多くこの本を読むまでは気づきませんでした。
子供と話す時はどうしても親という立場から話すと上から目線になってしまいがちですが、「ヨコの関係」が大切になってきます。
言葉がけも大事ですがまずは「ヨコの関係」を築いていくことから始めるのが重要になってきます。
この本では今回紹介しきれなかったものも含めると34の声かけの具体例と考え方が書かれています。
ぜひ、本書を読んで参考にしてみてください。
これからも子育て頑張っていきましょう!
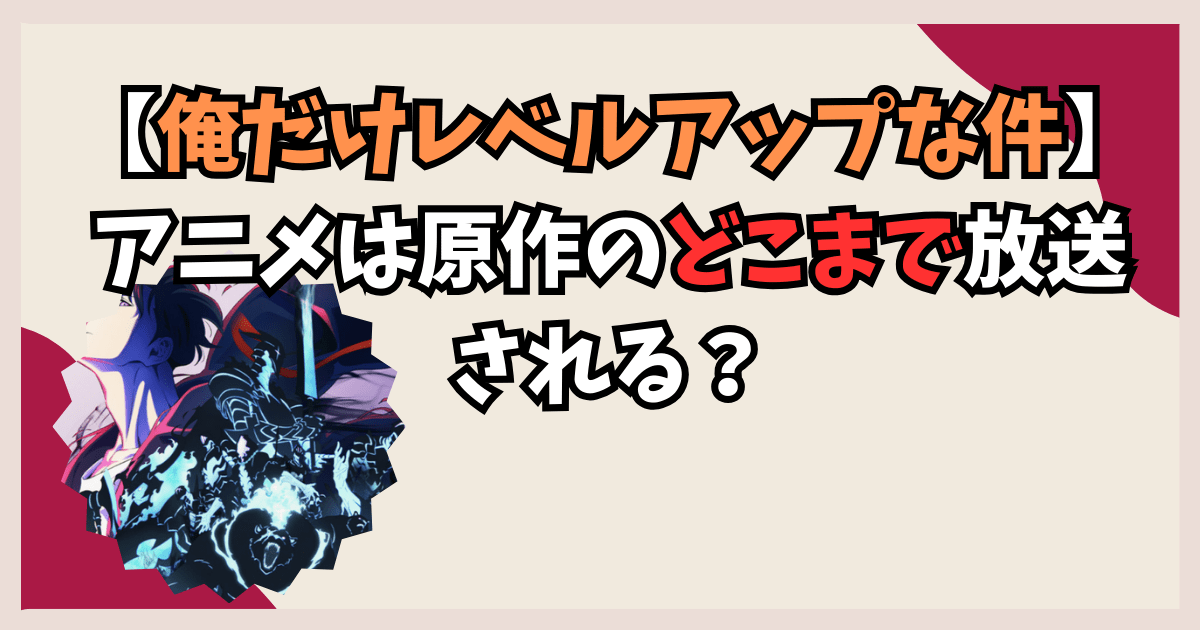
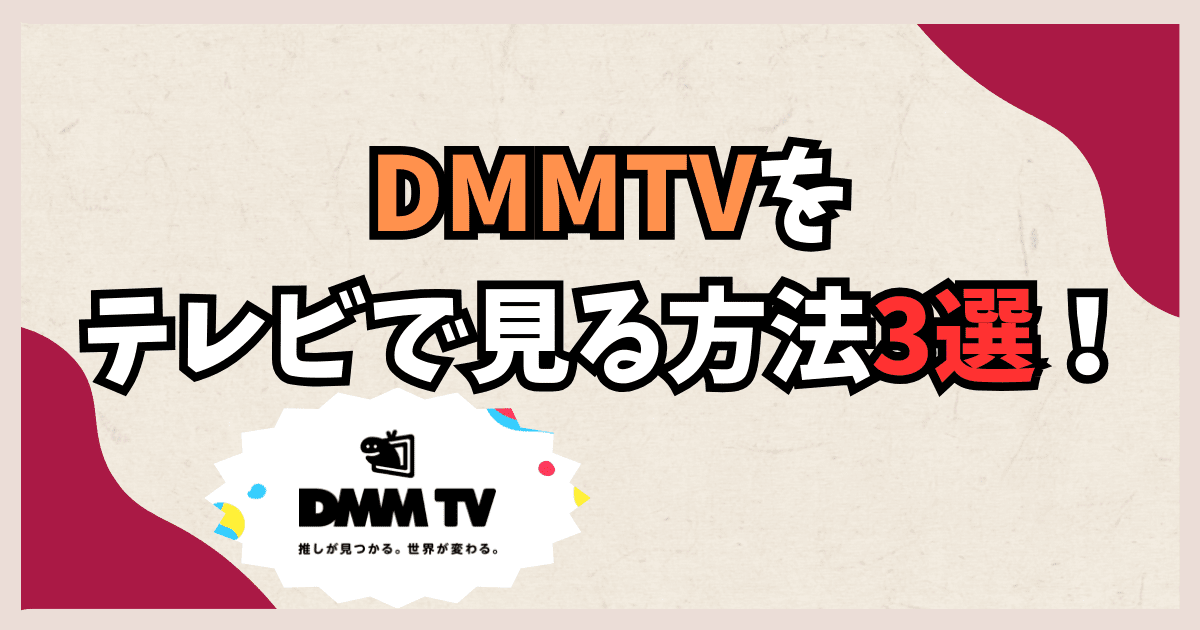
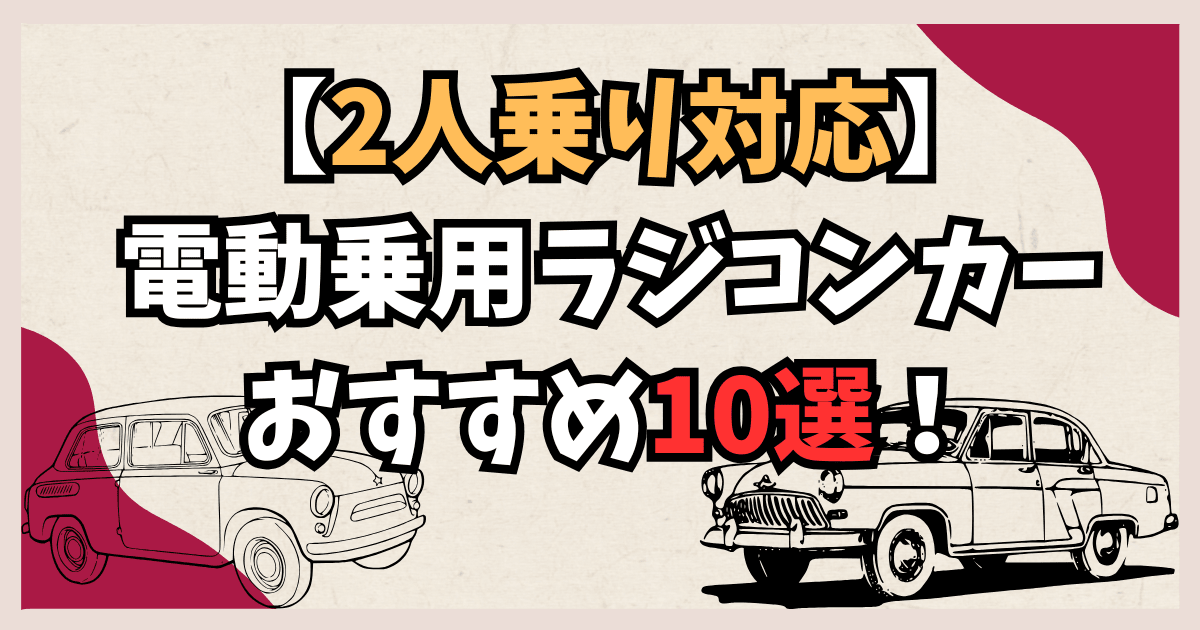

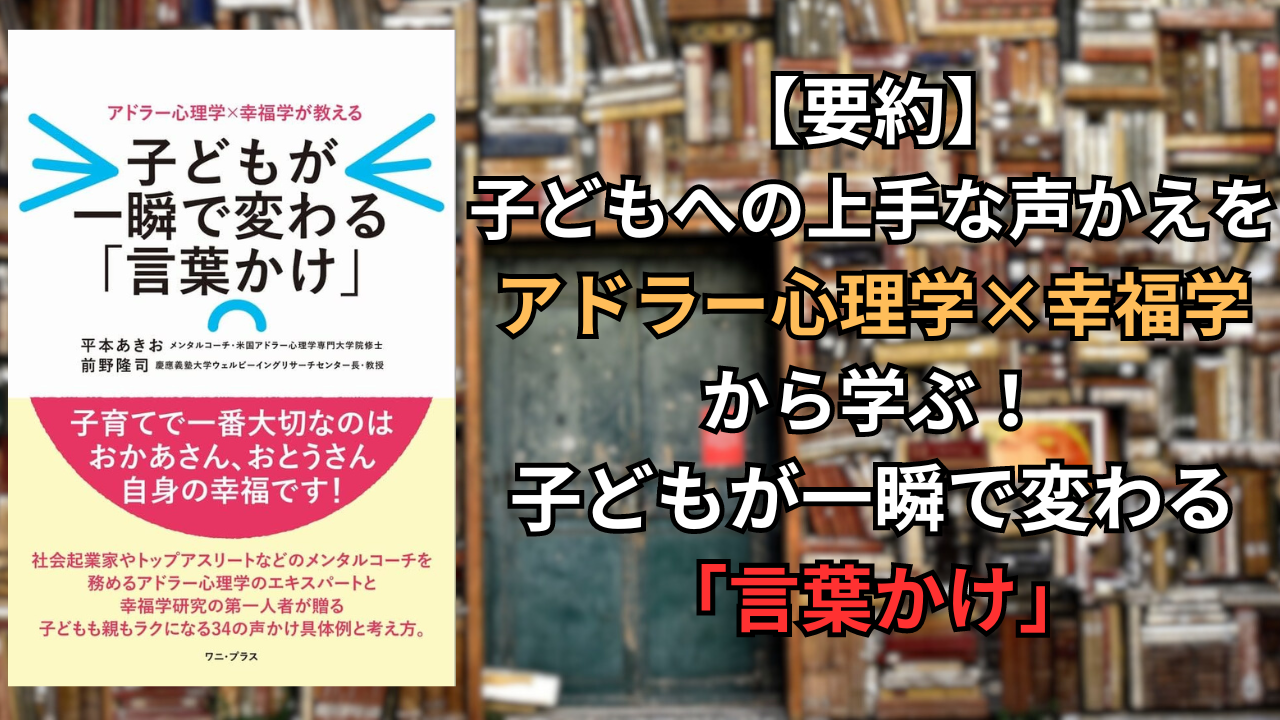
コメント